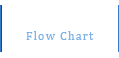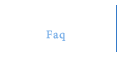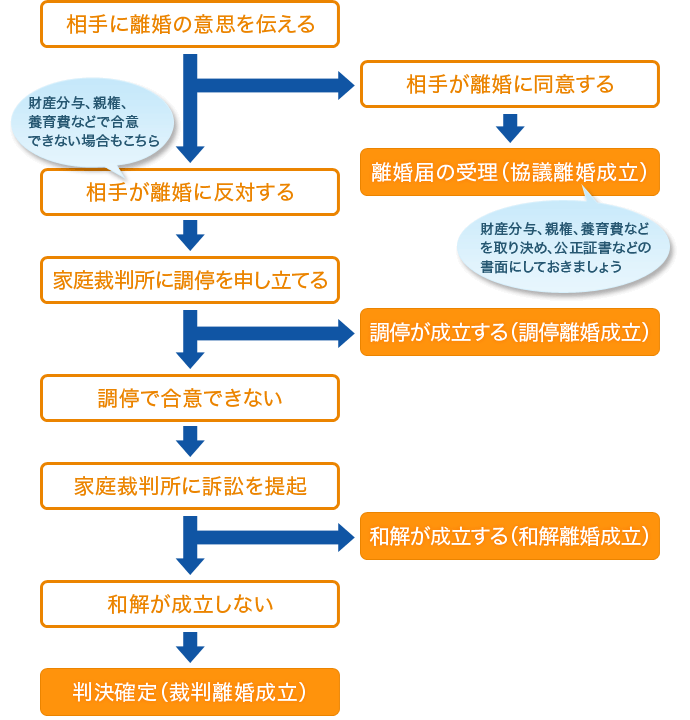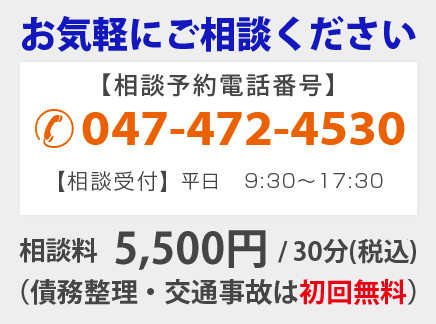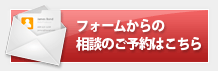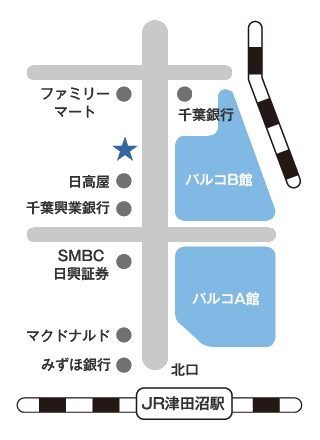知らないと損する離婚の種類と流れ~種類ごとのメリット・デメリット~
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士

目次
はじめに
このコラムをご覧の方は、夫または妻との関係に悩んでいて、今後その関係を清算するとした場合の流れを知りたいのではないでしょうか。
または、突然、夫または妻から離婚を切り出され、どうしたらいいのか、話がどういうふうに進んでいくのかを知りたいのかもしれません。
2020年には約19万3000組の夫婦が離婚したそうで、決して珍しいことではありませんが、あまり表に出てくる話ではないため、「じゃあ、実際、どういう流れで手続きするの?」と疑問をお持ちの方が多いと思います。
手続きは、まずは相手と話し合いをして、最後に「離婚届」を役所に提出してゴールです。
それは、基本的にはどの方も同じです。
しかし、相手から暴力を受けている、相手がどうしても離婚に応じない、子どもの親権でもめている、相手の居場所がわからない、、、人それぞれ事情が異なるため、最短コースでゴールにたどり着く方ばかりではありません。
そこに至るまでの道のりには、いくつか分かれ道があります。
ゴールに至るコースには、次の5種類があります。
| 相手の合意 | 裁判所の手続き | |
|---|---|---|
| 協議 | 必要 | 不要 |
| 調停 | 必要 | 必要 |
| 審判 | 不要 | 必要 |
| 裁判上の和解 | 必要 | 必要 |
| 裁判(判決) | 不要 | 必要 |
協議、調停、裁判上の和解は、相手との話し合いで合意できなければ、成立しません。
相手と合意できなければ、最終的には裁判で裁判官に判決を出してもらうことになります。
しかし、必ずしも裁判で希望どおりの判決が出るわけではありません。
協議で合意できなかった場合、調停、審判、裁判上の和解、裁判(判決)になりますが、いずれも裁判所での手続きが必要です。
離婚するときに決めること
「手続きは、まずは相手と話し合いをして」と前述しましたが、何について話し合えばいいのかわからない方もいらっしゃると思います。
「離婚」するかどうか
まずは、「離婚」するかどうか、です。
「絶対にしない!」ということもありますし、「財産分与で自宅をくれるならいいよ。」や「子どもの親権を譲ってくれるならいいよ。」などの条件をつけることもあります。
未成年の子どもの親権者
次に、絶対に相手と決めなくてはいけないことは、どちらが未成年の子どもの親権者になるか、ということです。
夫婦であるうちは共同で親権を行使しますが、離婚後は一方の単独親権になります。
離婚届に親権者を記入しないと受理されません。
(離婚後も共同親権を選べるように民法が改正されました。2026年(令和8年)5月までに、実際の運用が始まる予定です。)
親権者にならなかった親も、別居している親も、子どもの親であることは変わらないので、子どもに対する扶養義務は引き続きあります。一方で、親権者にならなかった親は、子どもの身上監護・財産管理について手を出せなくなります。
そして、いったん決めた親権者を変えるのは、決して簡単ではありません。
「とりあえず、早く離婚したいから、相手が親権者でもいいか」と安易に決めるのはやめましょう。
親権について詳しくは、「子どもの親権について」をご覧ください。
そのほか、決めておいた方がいいこと
そのほかに、相手と決めておいた方がいいことは、次の事項です。
- 未成年の子どもの養育費
- 未成年の子どもとの面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割の割合
これらは決めなくても離婚はできますが、一般的に届けを出した後に話し合うことが難しい上に、財産分与、慰謝料そして年金分割は請求する期限があります。そのため、届けを出す前に決めておくことをお勧めします。
相手と話し合いをして、離婚することは合意できたけれど、財産分与などほかの事項についてもめている場合、一方が離婚届に署名押印しないことが多いため、結局は次の段階である裁判所での調停に進むことになります。
手続きの流れ
どの手続きで離婚するかは、相手との合意のタイミング次第です。
「裁判所での手続きをしたくないから協議離婚がいい」と思っていても、相手が「絶対に離婚しない!」と言っている場合、いくら話し合いをしても合意できないので、次の手続きである裁判所での「調停」に進むしかありません。
離婚成立までの一般的な流れは以下の図のようになります。
とはいえ、この流れをあらかじめ知っているかどうかは、大きなポイントだと思います。
知らないままだと、相手に主導権を握られ、「あのとき、こうしていれば…」と後悔するかもしれません。
最初からわかっていれば、ご自身が望む最良の結果までの戦略を立てることが可能かもしれません。
また、それぞれの手続きにはメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 協議 |
|
|
| 調停 |
|
|
| 裁判上の 和解 |
|
|
| 裁判 (判決) |
|
|
ちなみに、手続きの違いによって、戸籍に記載される「離婚した日」の表示が変わります。
あまり戸籍を見る機会がないと思うので、ご存じない方が多いかもしれませんが、戸籍には出生や婚姻(結婚)、死亡などの身分関係が記載されています。
もちろん、離婚についても戸籍に記載されます。
出生については「出生日」(生まれた日)、婚姻については「婚姻日」(婚姻届が受理された日)、死亡については「死亡日」(亡くなった日)が記載されるのですが、離婚については手続きによって離婚した日の呼び方が変わります。
協議 : 「離婚日」(離婚届が受理された日)
調停 : 「離婚の調停成立日」
裁判上の和解 : 「離婚の和解成立日」
裁判(判決)・審判 : 「離婚の裁判確定日」
つまり、戸籍を見れば、どのような手続きで離婚したのか、わかるようになっています。
協議離婚
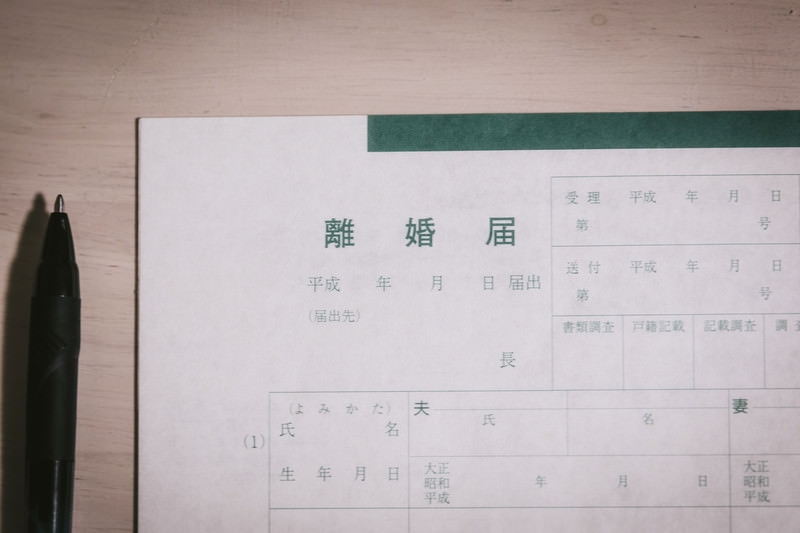
日本での離婚手続きで一番多いのは、協議離婚です。
相手と話し合い(協議)をして、届けを役所に出せば終わりなので、一番シンプルな手続きです。
協議離婚の場合は、「離婚届」が役所で受理されて、初めて「離婚した」ことになります。
協議のメリット・デメリット
メリット
協議離婚のメリットは、早く、お金をかけずに離婚できることです。
また、相手の不貞や暴力などの法律で決まっている事由がなくても、相手の同意があれば離婚できることです。
「法律で決まっている事由」というのは、裁判(訴訟)になったときに、裁判官に裁判上の離婚を認めてもらうための条件で、民法に定められています。
詳しくは、「裁判離婚するためには」をご覧ください。
デメリット
デメリットは、相手と直接話し合いをしなければいけないことです。
そのため、相手から暴力を受けている、相手の居場所がわからないなどの理由で話し合いができない場合などは、この方法では難しいでしょう。
弁護士に依頼するメリット・デメリット
相手との話し合いを弁護士に依頼することはできます。
そうすると、メリットである「お金をかけずに」はなくなってしまいますが、弁護士があなたの代わりに相手と話し合いをするので、デメリットである「相手と直接話し合い」はしないでもすみます。
相手から暴力を受けているなどの理由で相手と直接話し合いができない方は、弁護士を通して協議する方法を検討してみてください。
さらに、弁護士に依頼することによって、財産分与や養育費などについて、うっかり自分に不利な条件で合意するのを防げるメリットがあります。
財産分与でいうと、生命保険契約を解約した場合の解約返戻金額とか、退職した場合の退職金予定額などについても、結婚期間に応じた金額が財産分与の対象になります。
関係が悪化して相手から生活費の支払いがなくなってしまった場合は、離婚するまでの生活費に加え、支払われるはずだった生活費についても請求することができます。
弁護士であれば、裁判所の手続きをした場合に認められる条件で相手と交渉することができます。
とはいえ、弁護士に依頼すると着手金や報酬でまとまったお金が必要になりますので、まずは法律相談をして、ご自身の場合にどのような条件で相手と交渉した方が良いか、確認することをお勧めします。
話し合いで決めたことは書面に残す
相手との話し合いで合意できたら、子どもの養育費や面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料など、相手と決めたことについては書面に残しておく方がいいでしょう。
書面の記入例についても記載していますので、協議離婚を検討されている方は、「離婚届を出す前に決めておきたい6つのこと」もご覧ください。
なお、2012年(平成24年)4月から、協議離婚するときは、離婚後の子どもの養育費や面会交流について、子どもの利益を最優先に考慮して、話し合って決めるように民法に明記されました。
そこで、離婚届にも養育費や面会交流について決めたかどうかチェックする欄が設けられました。
勝手に届出されそうなときは、不受理申出を
相手があなたに無断で離婚届を提出してしまうと、「離婚した」ことになってしまいます。
本来は、届け出をするときに夫婦双方に離婚する意思がないと「無効」です。
しかし、役所の人は相手が勝手に届けを出したとはわからず、受理してしまいます。
「離婚届を偽造するなんて…」と驚かれるかと思いますが、実際に偽造した届出書を提出する人はいます。ほかにも、以前ケンカした勢いで署名押印した届出書を勝手に提出する場合もあります。
あなたに離婚の意志がないのに相手が勝手に届けを出した場合、無効を求めて裁判所での調停を申し立てる必要があります。調停で相手が無効について合意すればいいですが、調停に出席しなかったり、無効について合意しなかった場合は、さらに裁判(訴訟)を提起する必要があります。「無効」にするには、時間もお金も手間もかかります。
あなたが離婚したくない場合や相手との話し合いの最中で、まだ子どもの親権者等が決まっていない場合には、役所に「離婚届不受理申出書」を出しておくと、離婚届は受理されません。
調停離婚

相手と話し合いで合意できなかったときは、家庭裁判所に調停を申立て、第三者(調停委員)を間に入れて話し合うことになります。
相手との交渉が決裂しても、いきなり「裁判だ!」と訴えを起こすことはできません。「調停前置主義」というルールがあるからです。夫婦関係についての問題は、裁判官が白黒つける前に、もう一度調停という場で当事者同士話し合いましょう、ということです。
調停について詳しくは、「離婚調停ってどんなもの?」をご覧ください。
調停で合意できると、調停成立と同時に、「離婚した」ことになります。これが調停離婚です。
調停が成立すると、調停調書が作成され、合意した内容が調停条項に記載されます。
相手が調停条項の内容を守らなかった場合は、調停調書に基づいて、給与差押さえなどの強制執行をすることができます。
成立してから10日以内に「離婚届」を役所に提出する必要があるので、ご注意下さい。
10日以内に提出しなくても離婚が無効になることはありませんが、役所に提出したときに遅れた理由を問われたり、過料に処される可能性があります。
調停のメリット・デメリット
メリット
調停離婚のメリットは、第三者が間に入るので、相手と直接話さなくてよいこと、法律で決まっている事由がなくても、相手の同意があれば離婚できることです。
調停では、相手と交互に調停室に入って、それぞれ調停委員と話をします。
調停委員が双方の意見を聞いて、話し合いの仲介をします。
感情的対立が激しい場合やDV(家庭内暴力)がある場合は、相手と直接話をしないでもいいというのは、大きなメリットになるでしょう。
デメリット
デメリットは、月1回くらいのペースで平日に裁判所に行かなくてはいけないこと、離婚までに時間がかかることです。
調停は原則として当事者本人が裁判所に行く必要があるので、お仕事がある方などは負担に思われるかもしれません(遠方の裁判所で行われる場合は、電話会議システムを利用できる場合もあります。)。
また、相手が裁判所に出てこないとか、意見の対立が激しいとか、話し合いでの合意が難しいことが明らかな場合は比較的短期間で調停不成立になって手続きが終わりますが、多くの場合は合意までに半年以上時間がかかります。
調停を成立させる前に弁護士に相談しましょう
基本的に、調停はご本人だけで進められる手続きです。
ただ、調停では、調停委員が中立的な立場で話し合いをリードしてくれますが、最終的な目的は双方の合意です。
そのため、相手が自分の主張を強引に押してくるような場合、調停委員がこちらに譲歩を求めてくることがあります。
また、相手に弁護士が就くと、相手の意見に引っ張られていく可能性があります。
そして、調停委員は中立的な立場なので、「もっとこういう資料を出したら有利になりますよ」のような助言はしてくれないでしょう。
相手が出してきた案が、いくらご自身に不当な内容だったとしても、合意してしまえば、調停は成立してしまいます。
これは、逆もしかりで、ご自身に有利(相手に不利)な内容であっても、相手が合意すれば、調停は成立します。
成立した調停の内容を後で覆すことは非常に難しいです。
双方が合意すればどのような内容であっても調停成立するというのは、調停のメリットにもデメリットにもなりうることです。
上記のような場合がありますので、合意する前に弁護士に相談しましょう。
裁判になった場合を想定して、合意した方が良いのか、合意しないで裁判に進んだ方が良いのか、確認することをお勧めします。
裁判離婚・和解離婚
調停で合意できないと、調停不成立となり、調停は終了します。
次のステップは、裁判(訴訟)です。調停と裁判の違いについては後述します。
裁判のメリット・デメリット
メリット
裁判離婚のメリットは、法律で決まっている事由があれば、相手の同意なく離婚できること、弁護士に依頼すれば毎回裁判所に行かなくてもよいことです。
話し合いではどうにもならないときは、裁判にするほかありません。
裁判のポイントは、法律で決まっている事由の有無です。
そして、それを裏付ける証拠の有無も大事です。
それらがあれば、相手の同意がなくても、裁判離婚できる可能性が高いです。
デメリット
デメリットは、法律で決まっている事由がないと離婚できないこと、離婚までに時間がかかること、判決を下す場合は原則として本人尋問が行われること、弁護士に依頼すると費用がかかることです。
法律で決まっている事由がない、または事由があったとしても「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当」と判断されると、「原告と被告を離婚する」の判決は出ません。
また、裁判は法律の専門的知識が必要になるので、弁護士に依頼するのが一般的です。
そのための費用として、100万円以上かかると考えておいた方が良いです。
そして、途中で和解が成立しなかった場合は、原則として判決の前に本人尋問が行われます。
ドラマで見るような法廷で、相手の弁護士や裁判官から質問をされて、それに答えることになります。そしてその問答が証拠として扱われます。
さらに、裁判ではお互いの主張を書面にして裁判所に提出しますが、相手の書面にはうんざりするほどこちらの非が書かれており、多くの方が、精神的な負担を感じるようです。
裁判離婚とは

協議や調停は「話し合い」でしたが、裁判では双方が自分の考えを主張し、それを立証していきます。立証というのは、証拠を出して、事実を証明することです。
裁判離婚は、訴訟手続きを通じて最終的に裁判官が判断(判決)します。
法律で決まっている事由がなければ離婚の判決は出ません。
事由は、不貞行為や夫婦関係の破たん等ですが、詳しくは「裁判離婚するためには」をご覧ください。
裁判官が「原告と被告を離婚する」との判決を下し、その判決が確定すると、「離婚した」ことになります。これが裁判離婚です。
なお、「判決が確定」というのは、当事者が判決を受け取ってから2週間以内に不服申し立てをしなかった場合です。
判決の内容に不服があるときは、期限内に高等裁判所に対して「控訴(こうそ)」します。
当事者のどちらか、または双方が控訴すると、当事者が不服申し立てをした部分について高等裁判所の裁判官が再度審査します。その際、家庭裁判所で主張立証したものは控訴審に引継がれますが、当事者は家庭裁判所の判決に対して新たに主張立証することができます。
判決の確定で離婚した場合も、確定してから10日以内に「離婚届」を提出する必要があるので、ご注意下さい。
和解離婚とは
とはいえ、裁判でも、「話し合い」をすることもあります。
「和解」という手続きで、双方が歩み寄り、条件に合意できれば、和解成立と同時に「離婚した」ことになります。これが和解離婚です。
調停の話し合いで合意できないのに、なぜ裁判では和解できるのか不思議に思われるかもしれません。
これは、裁判官が出す判決が予想され、争っても無駄と思ったり、和解をした方が得と思われる場合、あるいはこれ以上争いを長く続けたくないという気持ちから互いに譲歩の姿勢がみられる場合などがあるからです。
裁判官は、訴訟手続き中、いつでも、何回でも和解を試みることができます。
裁判官からの和解の提案に当事者双方が応じると、交互に裁判官と話し合いを重ね、双方が合意できる和解内容を詰めていきます。
当事者が和解を拒否した場合は、訴訟手続きが進められ、最終的には判決が下されます。
和解成立で離婚した場合も、成立してから10日以内に「離婚届」を提出する必要があるので、ご注意下さい。
審判離婚
審判離婚は、両当事者が出頭できない場合など特殊な場合になされます。
審判離婚になることはほとんどありませんが、審判が確定したとき「離婚した」ことになります。
確定してから10日以内に「離婚届」を提出する必要があるので、ご注意下さい。
「調停」と「裁判」は、何が違う?

法律では、離婚の申立については「調停前置主義」といって、訴訟(裁判)を起こす前に、原則としてまず調停を申し立てることになっています。
そのため、話し合いで相手と合意できなかったときは、裁判所で決着をつけるために、まず「調停」を申し立てる必要があります。
そして、「調停」で合意できず、調停不成立で終了したときは、訴訟を起こすことになります。
なお、相手の居場所がわからない場合などは、調停を申し立てても相手を裁判所に呼び出すことができないため、調停をしないで、いきなり裁判をすることができるとされています。
詳しくは、コラム「居場所のわからない相手と離婚したい場合」をご覧ください。
離婚における調停と裁判は、同じ家庭裁判所で行われるため、手続の延長のように思われるかもしれませんが、まったく違うものです。
当事者の呼び方も違います。
調停では、裁判所に申立てをした方が「申立人」で、された方を「相手方」と呼びます。
裁判では、裁判所に提起した方が「原告」で、された方を「被告」と呼びます。
ただ、調停でも、裁判でも、最終的に決まった内容を守らないと、「調停調書」や「判決」、「和解調書」に基づいて、給与差押えなどの強制執行をすることができる点は同じです。
では、調停と裁判の特徴的な違いを以下でみていきます。
話し合いか法的判断か
「調停」と「裁判」の最も大きな違いは、「調停」は「話し合い」ですが、「裁判」は裁判官による「法的判断」だという点です。
「調停」では、調停委員が間に入って、相手と妥協点を探り合い、お互いに歩み寄りながら、合意を目指します。
そのため、合意が成立しなければ、離婚は成立せず、相手に離婚を強制することはできません。
また、自分の主張は書面ではなく口頭で調停委員に伝えることができます。
一方「裁判」では、当事者の主張が対立していても、最終的に判決を下す裁判官が、当事者がそれぞれ提出した「証拠」や裁判所の調査に基づいて事実を認定し、その上で、過去の事例(裁判例)が当てはまるか検討し、法律を適用して、離婚を認めるか否かを判断します。
そして、当事者は自分の主張を原則として書面にして提出します。
争いのある事実の認定の際、何よりも「証拠」がポイントになります。
極端にいうと、「証拠」のない事実は、事実とは認めてもらえない、ということです。
当事者は、それぞれの主張を認めてもらうため、「証拠」を提出して争います。
当事者の一方が離婚に反対しても、判決により認められると、離婚になってしまうので、強制力があるということになります。
そして、訴訟を提起しても、認められないと、請求は棄却され、離婚は成立しません。
ただ、裁判でも、「和解離婚」となることがあります。
裁判官から和解勧告され、当事者双方が和解案に合意できれば、和解調書が作成され、成立します。
法律で決まっている事由が必要か
「調停」では、当事者双方が合意すれば、経緯や理由にかかわらず、離婚できます。
一方「裁判」では、民法が定める事由(不貞行為、強度の精神病、婚姻継続が難しい重大な事情など)がないと、裁判官は離婚を認めてくれません(詳しくは「裁判離婚するためには」をご覧ください。)。
そのため、離婚したい方は、事由があることを「証拠」に基づいて主張立証する必要があります。
離婚したいけれど、事由があることの証拠がない方は、長期間の別居が「婚姻継続が難しい重大な事情」とされているため、別居期間をある程度延ばしてから、訴訟を提起することもあります。
注意が必要なのは、事由の責任が自分にある場合です。
夫婦関係を壊す原因を作った責任のある(有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)といいます。)方からの離婚請求は、原則として認められません。例えば、不貞をした、相手に暴力をふるった、などの事情があると、有責配偶者とみなされます。
公開か非公開か
「調停」は完全非公開で行われます。
調停では、当事者が交代で調停室に入って、調停委員に自分の意見を述べますが、調停室に入れるのは当事者と当事者の代理人である弁護士だけです。
付き添いに来た家族は、原則として調停室に入ることはできず、待合室で待つことになります。
一方「裁判」は原則として公開の法廷で行われます。
ドラマの裁判シーンで出てくるようなイメージです。そのため、傍聴席に一般の人がいる可能性があります。
ただ、裁判の手続きには「口頭弁論期日」や「弁論準備手続期日」などがあり、「口頭弁論期日」は公開の法廷ですが、「弁論準備手続期日」は法廷以外の準備室等で行われ、必ずしも公開ではありません。
終わるまでの期間
「調停」も「裁判」も、裁判所に申立書(訴状)を出して、1か月後くらいに第1回期日が指定され、相手方(被告)に裁判所から呼出状が送付(送達)されます。その後、月1回くらいのペースで行われます。
「調停」は、離婚の合意ができる見込みがあれば、当事者双方が関係資料(給与明細、源泉徴収票、通帳コピーなどの財産資料等)を出して、解決金額などのすり合わせをしていくので、半年~1年程かかります。
未成年の子どもの親権について争っている場合、親権者が決まらないと離婚できないので、離婚の合意は難しく、早めに調停不成立で終わりになることが多いです。
一方「裁判」では、最終的に裁判官が判断するための材料(主張、証拠、調査官調査報告書など)が揃うまで続きます。
調停で出した資料も、再度証拠として出し直します。
当事者双方の言い分を記した陳述書を証拠として提出し、本人尋問で述べたことも証拠として扱われます。
相手が出てこない場合や、ただ離婚の判決のみを求める場合には半年程で終わることもありますが、多くは1年程度、あるいはそれ以上かかります。
かかる費用
「調停」は、弁護士に依頼しない場合は、あまり費用はかかりません。申立書に貼る1200円の印紙、裁判所に予納する郵便代、申立書に添付する戸籍謄本の取寄せ費用として、合計3000円くらいあれば大丈夫です。
一方「裁判」では、専門的な知識が必要になってくるので、弁護士に依頼される方がいいでしょう。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、報酬まで含めると、100万円以上になることがあります。
また、訴状に貼る印紙は最低でも1万3000円かかります。
裁判所からの呼び出しに応じなかった場合の影響
相手から「調停」を申立てられると、裁判所から申立書のコピーと一緒に「期日呼出状」が送られてきます。
もちろん呼び出された日時に裁判所に行って、調停に出席して、ご自身の気持ちを伝える方が良いですが、出席は強制ではありません。出席しないままだと、調停は不成立で終了します。
一方、相手から「裁判」を提起されると、裁判所から訴状のコピーと一緒に「期日呼出状」が送られてきます(特別送達という特別な方法の郵便です。)。
ここまでは調停と一緒ですが、被告(訴えられた人)が裁判の期日に出席しないからといって、裁判の手続きが終わるわけではありません。出席しないと、そのまま裁判の手続きが進められて、原告(訴えた人)の主張どおりに判決が出ることになります。
裁判所から訴状が届いたら、そのまま放置せず、すぐに開封して内容を確認しましょう。
まとめ
離婚に至る過程ごとに上記のような違いがあるため、ご自分の状況によって選択は変わってきます。
長年連れ添っているご夫婦の場合は、協議離婚でも財産分与と年金分割はきっちり計算して決めた方がよいです。ご夫婦で分け合う金額が高くなることが多いからです。
財産分与や年金分割は、原則として夫婦2分の1ずつ分け合うのですが、なかには「おまえの貢献度は2分の1もない」というようなことを言う方もいらっしゃいます。また、自分が親の相続で受け取った財産については財産分与の対象にならないのですが、ご存じない方もいらっしゃいます。
正しい知識を持って相手と話し合いをしないと、ご自分が損をすることになりかねません。
相手に不貞行為があるなど慰謝料請求も一緒にしたい場合、ご自分に有利な「証拠」がないときには、少し妥協してでも調停を成立させるとか、逆に決定的な「証拠」があるときには、一切妥協せずに調停を不成立にして、離婚訴訟にするなど、戦略的な判断が必要になります。
そのような判断には、専門知識と豊富な経験が重要になります。
ご相談者のなかには、手続きが進んでからご相談にいらっしゃる方もいらっしゃいますが、そうすると選択肢が少なくなってしまいます。
できれば、なるべく早い段階でご相談にいらっしゃった方が良いでしょう。
そうすれば、半年後、1年後、2年後先を見据えたうえで、今何をすればいいのか、具体的にアドバイスをすることができます。
離婚する前に、ご自身の場合はどのような選択をした方がいいか、専門家である弁護士に相談しましょう。