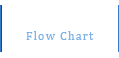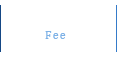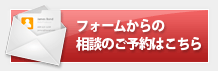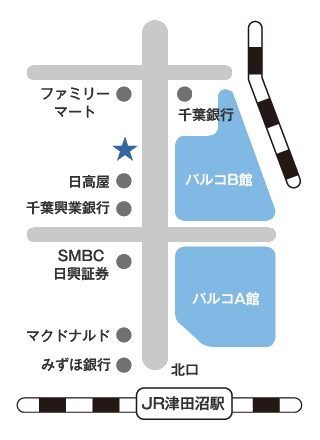裁判離婚するためには
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士

はじめに

「知らないと損する離婚の種類と流れ」に、離婚に至る手続には、大きく分けて5つの段階があるとお伝えしました。
- 協議・・・夫婦で話し合い→離婚届を提出
- 調停・・・協議で合意できなかった
→家庭裁判所の調停で話し合い
→合意できれば調停成立
→離婚届を提出 - 裁判上の和解・・・調停で合意できなかった
→家庭裁判所の裁判(訴訟)手続き
→合意(和解)できれば和解成立
→離婚届を提出 - 審判・・・調停で合意できず、両当事者が出頭できない場合等
→裁判所の判断(審判)確定
→離婚届を提出 - 裁判・・・調停で合意できなかった
→家庭裁判所の裁判(訴訟)手続き
→裁判官が判断(判決)して確定
→離婚届を提出
の5つです。
上記の「合意」というのは、離婚することについての合意はもちろんのこと、未成年の子どもの親権者、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料などについての合意があります。
離婚のときに必ず決めないといけないのは未成年の子どもの親権者だけですが、多くの場合、離婚は夫婦関係の清算なので、その他の事項についても協議をして、合意を目指します。
そして、裁判離婚では、訴訟手続を通じて最終的に裁判官が訴えの内容を判断しますが、相手(裁判では被告と言います)が離婚を拒否している場合、法律で決まっている事由がなければ離婚の判決は出ません。
また、訴訟を提起した方(裁判では原告と言います)は、法律で決まっている事由があることを、立証(証拠に基づいて事実を証明)する必要があります。
では、裁判で離婚請求が認められる「事由」とは何でしょうか。
上記のように、裁判は手続きの最終段階です。
ご自身、または相手に「事由」があるか、ないかで、手続きの選択が変わってくる可能性があります。
今回は、裁判で離婚が認められるための「事由」についてみてみましょう。
裁判上の離婚が認められる事由(民法第770条)
裁判で離婚するために必要な「事由」は、民法第770条に書いてあります。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
上記一~五の事由のいずれかに当てはまり、今後夫婦関係が改善する余地がないことが明らかなときに、離婚請求は認められます。
上記一と二は、配偶者(夫または妻)が有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)の場合で、上記三~五は、夫婦関係が破たんしている場合と言えます。
実務上では、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を理由に訴えを提起することが多い印象です。
抽象的な表現で、具体的にイメージしにくいと思います。どのような場合に当てはまるのかは、後述します。
有責配偶者

有責配偶者とは、夫婦関係を壊す原因を作った責任のある配偶者のことです。
不貞行為
事由の一にある「不貞行為」は、配偶者以外の者と性的関係を持つことを言います。
法律で直接的に書かれてはいませんが、夫婦は当然に貞操義務を負うこととされています。
不貞行為は、貞操義務に違反し、夫婦関係を壊す原因となるため、事由となっています。
なお、不貞行為とされる「性的関係」は、自由な意思に基づく性交渉とされています。
そのため、相手の不貞行為の証拠として、相手が不貞相手と思われる人物と手をつないでいる写真では証拠として弱いですし、相手が第三者と二人でラブホテルから出てきた写真は強い証拠と言えるでしょう。
悪意の遺棄
結婚すると、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条)
という、同居・協力・扶助義務が発生します。
また、扶助義務に加えて
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する。」(民法第760条)
とされており、資産や収入に応じて生活費を負担する義務があります。
夫婦関係を壊すかもしれないと知りつつ、「同居・協力・扶助義務」「生活費を負担する義務」に違反すると、事由の二にある「悪意の遺棄(あくいのいき)」とされる可能性があります。
夫婦の義務は、夫婦としての必要最低限の条件のようなもので、それを守らず、結果として夫婦関係が壊れると、有責配偶者と言われても仕方がないということです。
具体的には、夫婦関係を壊そう、または壊れてもいいと考えて、
- 相手の了解なく別居する
- 相手が自宅を出ていかざるを得ない状況にした
- 相手に生活費を渡さない
などが悪意の遺棄と考えられます。
なお、仕事で単身赴任する場合や病気療養のために別居する場合などは、同居義務違反にはなりません。
実務的には、よほどひどい場合(半身不随の妻を置き去りにして別居や、暴力で妻が別居するように仕向けて生活費も渡さないなど)に悪意の遺棄と判断されるようです。
悪意の遺棄とまでは言えない場合でも、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に当たるとして、離婚が認められることがあります。
夫婦関係の破たん

夫婦関係が壊れてしまって、共同生活が改善する見込みがない状態を「夫婦関係の破たん」と言います。
しかし、夫婦関係が破たんしているかどうかを客観的に判断するのは、難しいことです。
心の中は誰にも見えませんし、夫婦のあり方は千差万別で、夫婦の一方が「もうやり直せない」と感じていても、何かのきっかけでやり直せることがあるかもしれません。
裁判官は、次の事情を総合的に考慮して、夫婦関係が破たんしているかどうか、離婚が相当かどうかを判断します。
- 社会常識的に離婚請求の理由が認められるものかどうか
- 結婚生活中の様子や子どもの有無
- やり直す気持ちの有無
- 当事者の年齢・収入・財産など
夫婦関係の破綻が認められる事例
事由の五「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」はとても抽象的な表現ですが、今までの裁判官の判断(裁判例)では、配偶者に次のような事情がある場合に破たんが認められています。
- 暴力・虐待
- 重大な侮辱
- 犯罪行為
- 働かない、収入に見合わない浪費、不要な借金など経済的理由
- 配偶者の親族との不和解消に尽力しなかった
- 過度な宗教活動
- 円満な性生活を妨げる事情
- 病気や身体障がいで協力義務を果たせず、これ以上看病等で犠牲を強いるのは酷である
- 性格の不一致
- 長期間の別居
そのため、夫婦関係は破たんしているけれど、裁判官に認められるような証拠がないような場合、「長期間の別居」の状態を作って、「婚姻を継続し難い重大な事由」とすることがあります。
「長期間の別居」は、夫婦関係が破たんしていることを客観的に示す事情となります。
とはいえ、単身赴任や別居婚で夫婦円満な場合もありますし、同じ家で寝起きしていても会話がなく、食事、寝室、洗濯、掃除など別々で生活している場合もあります。
夫婦としての共同生活の実体があるかどうか、今後同居生活を復活させる意思があるかどうかが、重要となります。
では、「長期間の別居」とは、どのくらいの期間のことを言うのでしょうか。
実は、「長期間」は明確に決まっているわけではありません。
これまでの裁判例では、3~5年の別居期間で破たんが認められているようです。
ただ、上記のような事由がある場合でも、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚は認められません。
有責配偶者からの離婚請求
事由の五「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」としても、夫婦関係を壊す原因を作った責任のある配偶者からの請求は、原則として認められません。
離婚したい配偶者が「婚姻を継続し難い重大な事由」を作れば離婚できることになるからです。
しかし、夫婦関係が完全に破たんしていて、改善する見込みが全くなく、離婚請求が正義・公平の観念、社会的倫理観、信義誠実の原則に反するとはいえないときは、有責配偶者からの離婚請求でも認められる可能性があります。
「反するとはいえないとき」の判断については、
- 有責配偶者の責任の内容・程度
- 相手方配偶者の結婚生活を続ける意思と有責配偶者に対する感情
- 離婚を認めた場合の相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態
- 夫婦間の子への影響
- 別居後の生活関係(内縁関係を築いていることや婚外子がいるなど)
- 時の経過が上記の事情に与える影響
を考慮するとされており、特に
- 夫婦の別居が両当事者の年齢と同居期間との対比において相当の長期間
- 経済的に独立していない子どもがいない
- 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的にきわめて苛酷な状態に置かれることがない
という条件すべてに当てはまる場合に、有責配偶者からの離婚請求でも認められると判断されたことがあります(最高裁大法廷判決昭和62年9月2日)。
さいごに
夫婦間の話し合いや家庭裁判所での調停でも合意できずに裁判になる場合、離婚については同意しているけれども親権や財産分与、慰謝料などの問題で対立している場合が多いです。
しかし、なかには「絶対に離婚したくない」と言って裁判になることもあります。
そのときは、離婚したい方は裁判上の離婚が認められる事由があることを証拠を示して主張することになり、離婚したくない方はそれを争うことになります。
判断するのは裁判官ですが、裁判官の家族観や考え方によって結果が違ってくる可能性はあります。
裁判では専門知識が必要になりますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。