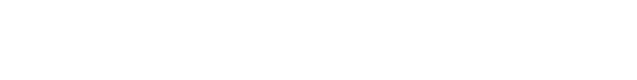コラム記事一覧
相続の制度
相続は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」「特別受益」「遺留分」「寄与分」「特別の寄与」「配偶者居住権」など、様々な制度があります。
そして、これらの制度を知らないと、損する可能性もあります。
相続の制度について、わかりやすく解説しています。
主なテーマ:法改正対応、配偶者居住権、相続土地国庫帰属、遺産分割期限、相続放棄、遺留分制度
- 相続土地国庫帰属制度の申請方法について
- 相続土地国庫帰属制度について
- 遺産分割に期限ができた?!2023年4月から変わること
- 配偶者居住権とは?利用した方が良い場合・良くない場合
- 遺産分割調停とは?~利用方法や調停の進め方、税金面の注意事項について~
- 改正法の内容を徹底解説(第4回)~遺留分制度、特別寄与料、持戻し免除の意思表示の推定規定について~
- 改正法の内容を徹底解説(第3回)~遺産分割制度、相続の効力等について~
- 改正法の内容を徹底解説(第2回)~自筆証書遺言制度、配偶者居住権制度について~
- 改正法の内容を徹底解説(第1回)~改正の背景について~
- 単純承認及び限定承認
- 相続放棄とは?法的な効果や活用法、手続の仕方について
- 特別受益って何? 仕組みや計算方法について
- 法改正に対応 寄与分と特別寄与料について
- 相続人がいない?そんなときは相続財産清算人!
- 3ヶ月過ぎてからの相続放棄ってできる?
- 相続放棄・代襲相続があった場合の相続人
- 遺留分って何?
- 相続人とその法定相続分について
- 相続に関するタイムリミット(期限)
相続の手続き
「何から手をつけて良いかわからない」は多くの方の共通の悩みです。相続手続きは「時間との勝負」であり、適切な順序で進めなければ後で大きなトラブルや不利益を招く可能性があります。
相続手続きの全体の流れの解説と、戸籍収集による相続人確定、遺言書探索・検認手続き、相続放棄手続きをご自身でする方法を詳しく紹介しています。
主なテーマ:手続きの流れ、戸籍収集方法、遺言書探索、相続財産調査、期限管理
遺産分割
遺産分割の話し合いが整った後の遺産分割協議書の書き方を文例付きで紹介しています。
また、遺産に自宅不動産がある場合の遺産分割について事例をあげて解説しています。
主なテーマ:遺産分割の進め方、不動産の分割方法、協議書作成、税務対策、紛争予防
遺言書のこと
遺言書は単に書けば良いものではなく、法律で決まっているルールを守ることが重要です。
2020年7月開始の自筆証書遺言保管制度により、自筆証書遺言がより安全便利になりました。
遺言書の訂正・書き換え方法、遺言執行者の役割・責任など、確実に実現する実務知識を文例付きで解説しています。
主なテーマ:遺言書の種類と選択、自筆証書遺言保管制度、遺言執行者、訂正・変更方法、文例・書き方