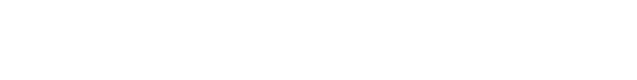よくある質問
1. 生前対策、亡くなる前にできること
遺言書は必ず作成する必要がありますか?
遺言書の作成は法律上の義務ではありませんが、財産の分配を明確にし、相続人間のトラブルを防ぐために強くお勧めします。特に複雑な家族関係や大規模な資産がある場合は重要です。
遺言書の作成にはどのような方法がありますか?
主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分で書くため費用がかかりませんが、方式に厳格な要件があります。要件を満たさないと遺言としての効力が発生しないので注意が必要です。
公正証書遺言は公証人の関与で作成するため、法的な安全性が高いです。
生前贈与のメリットは何ですか?
生前贈与のメリットには、相続税の節税、財産の早期移転による後継者の育成、贈与者の意思の明確な伝達などがあります。基本的に贈与を受けた人は贈与税を支払う必要がありますが、控除や非課税制度を利用すると負担が軽くなる可能性があります。ただし、遺留分の侵害、特別受益とされる、定期贈与とみなされる可能性に注意が必要です。また、贈与時期によっては相続税の課税対象となる場合もあります。
家族信託とは何ですか?
家族信託は、自身の財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を委ねる仕組みです。認知症になった場合の財産管理や、相続対策として活用できます。
エンディングノートは法的効力がありますか?
エンディングノートには法的拘束力はありませんが、遺言の補足資料として、また家族への思いを伝える手段として有用です。ただし、法的に効力を持たせたい内容(遺産の分け方、遺贈、死後認知など)は遺言書に記載すべきです。
相続時精算課税制度とは何ですか?
60歳以上の親から20歳以上の子への贈与で、将来の相続財産に加算して相続税を計算する制度です。2,500万円までの基礎控除があり、生前贈与と相続税の節税を両立できる可能性があります。
任意後見制度を利用するメリットは何ですか?
認知症などで判断能力が低下した場合に備え、財産管理や身上監護を行う人を事前に決めておける制度です。財産の保護や適切な介護サービスの利用などが円滑に行えるメリットがあります。任意後見制度について詳しくは、当事務所のコラム「任意後見制度について」をご覧ください。
葬儀や埋葬について事前に準備できることはありますか?
葬儀の形式や規模、埋葬方法(土葬・火葬)、お墓の選択などを事前に決めておくことができます。エンディングノートに記載したり、家族と話し合っておくことが大切です。
相続税対策として、どのような方法がありますか?
主な方法として、生前贈与、相続時精算課税制度の利用、不動産の評価額の引き下げ、生命保険の活用、法人の設立などがあります。個々の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
自社株の承継対策として何ができますか?
種類株式の発行、持株会社の設立、株式の生前贈与、経営承継円滑化法の特例の活用などがあります。早期からの計画的な対策が重要で、税理士や弁護士など専門家との相談をお勧めします。
2. 葬儀後、亡くなった後の手続き
相続手続きを進めるための必要書類を教えてください。
亡くなった方の出生から現在までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、親族関係図、遺産に関する書類(不動産の権利証や登記識別情報、預金通帳、株式等の取引残高報告書等)などがあるといいでしょう。取得が難しいときは、弁護士が代理人として取寄せられるものもありますので、ご相談ください。
相続の手続きはいつまでに完了させる必要がありますか?
遺産分割をする期限はありませんが、相続放棄と限定承認の申述は、自分が相続人となることを知ったときから3か月以内に手続きする必要があります。
また、遺留分がある場合は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年か、亡くなったときから10年を経過したときに遺留分侵害額の請求をする権利がなくなります。さらに、亡くなったときから10年経過後は、原則として特別受益・寄与分の主張ができなくなります。
なお、相続税の申告が必要な方は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を税務署に提出する必要があります。亡くなった方に所得があった場合については、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告と納税をする必要があります。
遺産分割をする期限がないとはいえ、ずっと放っておくと相続人が亡くなってその方の子が相続するなど複雑になってしまいます。また、令和6(2024)年4月1日から不動産の相続登記が義務化され、相続人は取得を知ってから3年以内に登記申請をしないと罰則が適用されるようになりましたので、なるべく早く手続きすることをおすすめします。
相続放棄をするにはどうすればいいですか?
相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があります。亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、所定の申述書と亡くなった方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・住民票、申述人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等を提出します。期限は自分が相続人となることを知った日から3ヶ月以内です。なお、プラスの財産はないのに、期限後に借金のあることが判明した場合、期限後でも放棄できる場合があります。
相続税が払えないので相続放棄したいのですが、ご対応可能でしょうか。
相続放棄の申述を受任することは可能です。
本当に相続放棄をした方がいいのか、まずはご相談者のお話を伺って今後へのご案内をいたします。
遺言書がない場合、どのように遺産を分割すればいいですか?
民法に亡くなった方との続柄ごとに遺産を引き継ぐ割合が決められているので、それに基づいて分割するか、相続人全員の合意による協議分割を行います。合意形成が難しい場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
親の四十九日が終わって、兄から「署名押印して印鑑証明書を付けて返送するように」と遺産分割協議書が送られてきました。兄が「早くしろ」と催促するので、署名押印して印鑑証明書と一緒に返送しました。今から内容を変更できますか。
原則として、一度書面に書いてあるものに署名押印してしまうと、その内容を変更するのは難しいと言えます。
一方で、遺産分割協議書の内容について思い違い(錯誤)があった、兄がだますようなことを言った(詐欺)など、取り消すことができる場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
ずっと疎遠だった弟に親の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。
民法では、亡くなった方との続柄によって遺産を引き継ぐ割合が定められています。法律では個人的な事情を規定するのは難しいからです。ただ、その事情を遺産分割で考慮できるように、寄与分や特別受益などの制度があります。
自分は長年親の世話をしていたのに、何もしていない弟が自分と同じ額を引き継ぐのは不公平に感じるかもしれません。家族関係は十人十色でそれぞれ事情が異なります。遺産分割についてわからないことや不安なことがありましたら、弁護士にご相談ください。
相続人が行方不明の場合はどうすればいいですか?
行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。選任された管理人が不在者に代わって手続きを行います。
預貯金の相続手続きはどのように行いますか?
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人の印鑑登録証明書などを用意し、金融機関に手続きを申請します。各金融機関によって所定の申請書があり、必要書類が異なる場合があります。
遺産に借金がある場合はどうなりますか?
原則として、相続人は亡くなった方の借金も民法で定められた割合で引き継ぎます。ただし、相続放棄や限定承認の手続きを行うことで、借金を引き継ぐことを回避したり、プラスの相続財産の範囲内に限定したりすることができます。
相続登記は必ず行う必要がありますか?
2024年4月1日以降、相続により不動産を取得した場合、原則として3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。登記を怠ると過料が科される可能性があります。
遺言執行者の役割は何ですか?
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きを行う人です。財産の調査、遺産の管理、遺贈の履行、債務の弁済などを行います。遺言書で指定するか、必要に応じて利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。
相続税はどのように計算されますか?
相続税は、課税遺産総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を引いた金額に税率を乗じて計算します。ただし、各種の控除や特例があるため、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
相続税の納付が困難な場合、どのような対応ができますか?
納税が困難な場合、延納(最長20年)や物納(不動産や有価証券で納付)の制度があります。また、事業や農地の承継に関する特例措置もあるため、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士と司法書士のどちらに相談するのが良いのでしょうか。
司法書士は、不動産登記の専門家です。遺産に不動産があり、すでに遺産の分け方が決まっているような場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。
遺産が多い、相続人の間で分け方が決まらない、生前贈与や寄与分などの問題があるなどの場合、弁護士に相談することをおすすめします。
受任してもらえないのは、どのような場合でしょうか。
ご相談者のご希望を叶えることが難しい場合や、仮に受任したときにご相談者が得られると予想される金銭的利益よりも弁護士費用の方が多額になると見込まれる場合など、理由をご説明してご依頼をお断りすることがあります。
例えば、次のようなケースはご依頼をお受けすることは難しいです。
- ・ご相談者は法定相続人でも親族でもなく、遺言もないけれど、長年亡くなられた方のお世話をしていて、いくらかでも遺産を受け取りたいとのご希望をお持ちの場合、法定相続人が遺産を引き継ぐ限り法律上ご相談者が遺産を受け取る権利はないため、ご依頼をお受けすることは難しいです。
- ・法定相続人がご相談者と認知症の母親で、母親に成年後見人をつけずに遺産分割したいとのご希望をお持ちの場合、法律上認知症の方が単独で遺産分割協議をすることはできないため、ご依頼をお受けすることは難しいです。
- ・ご相談者が生前亡くなった方の預金口座からキャッシュカードを使って勝手に500万円を引き出したところ、共同相続人である弟から返還するように請求されていて、亡くなった時点の遺産が合計300万円だった場合、法律上ご相談者が受け取れる遺産はなく、弟に100万円を支払うことになるため、ご相談者が弁護士費用を負担してまで弁護士に依頼するメリットがないので、ご依頼をお受けすることは難しいです。
3. 知っておきたい基礎知識
法定相続人とは誰のことですか?
法定相続人は、民法で定められた遺産を引き継ぐ権利のある人のことです。第一順位は子(代襲相続人を含む)、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹です。第一順位がいない場合は第二順位に、第二順位がいない場合は第三順位に権利が移っていきます。配偶者(夫・妻)は常に引き継ぐ権利があります。
代襲相続とは何ですか?
代襲相続とは、本来の相続人が相続開始前に死亡している場合や相続欠格、相続廃除があった場合に、その人(本来の相続人)の子が代わりに遺産を引き継ぐことです。
例えば父親が亡くなって、父親よりも前に長男が亡くなっていた場合、長男の子ども(父親の孫)が代襲相続人になります。長男の子どももすでに亡くなっているときは、長男の孫(父親のひ孫)が代襲相続人になります。兄弟姉妹が相続人の場合でも代襲相続はありますが、亡くなった方の甥、姪までです。甥、姪の子どもには代襲相続しません。
代襲相続人は本来の相続人が受けるはずだった割合で遺産を引き継ぐ権利を得ます。
遺産を引き継ぐ割合はどのように決まりますか?
遺産を引き継ぐ割合は、民法で定められています。
相続人が配偶者(夫・妻)と子の場合は2分の1ずつ、配偶者と親の場合は配偶者が3分の2で親が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3で兄弟姉妹が4分の1です。
子、親、兄弟姉妹が数人いる場合、各自の引き継ぐ割合は、同順位の者と等分したものになります。ただし、父だけ同じ、母だけ同じ兄弟姉妹は、父母ともに同じ兄弟姉妹の2分の1の相続分になります。
配偶者がいない場合は、全部を同順位の者と等分することになります。
例えば、配偶者と子3人の場合、配偶者は2分の1、子は2分の1を3人で等分するので6分の1ずつになります。
配偶者と兄弟姉妹4人で、そのうち兄1人がすでに亡くなっていて甥2人が代襲相続する場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1を4人で等分するので16分の1ずつ、さらに甥2人は16分の1を2人で等分するので32分の1ずつになります。
相続開始はいつの時点ですか?
相続開始は亡くなった時点です。この時点で相続人が確定し、遺産の帰属や相続税の計算基準日となります。
遺留分とは何ですか?
遺留分は、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。
配偶者(夫・妻)と子は民法で定められた遺産を引き継ぐ割合の2分の1、直系尊属のみの場合は3分の1が遺留分となります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、亡くなった方に妻と子2人がいて、遺言に「すべての遺産を妻に相続させる」と書いてあった場合、子2人はそれぞれ民法で定められた割合4分の1(2分の1の2分の1)のさらに2分の1、8分の1の遺留分について妻(子の母親)に請求することができるということです。
特別受益とは何ですか?
特別受益とは、亡くなった方から生前に贈与を受けたり、死因贈与(贈与者の死亡によって効力が生じる契約による贈与)や遺贈(遺言による贈与)を受けるなど、特別な利益を得た者が共同相続人の中にいる場合の、その特別な利益のこと、あるいは利益を受ける行為自体をいいます。そして、特別受益を受けた者を特別受益者といいます。特別受益がある場合には、相続人間の公平を図るため、遺産分割の際に、亡くなった時の実際の遺産に特別受益分を加えたものを遺産とみなして分け方の算定を行うことができます。
寄与分とは何ですか?
寄与分とは、亡くなった方の療養看護や財産の維持増加に特別に貢献した相続人が、通常の民法で定められた割合の取り分に加えて取得できる取り分のことです。相続人間の協議や家庭裁判所の審判で決定されます。
なお、相続人以外の親族が亡くなった方の療養看護を無償で行っていたなどの事情がある場合、その親族は相続人に対して特別寄与料を請求することができます。
生命保険金は遺産に含まれますか?
生命保険金は原則として遺産には含まれません。受取人に指定された人の固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。ただし、生命保険金の額や遺産総額に対する比率、受取人と亡くなった方との関係などによっては特別受益とみなされる可能性があります。
相続税の基礎控除額はいくらですか?
相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円となります。
相続時精算課税制度と暦年課税制度の違いは何ですか?
相続時精算課税制度は、生前贈与を将来の相続財産に加算して相続税を計算する制度で、2,500万円の特別控除があります。暦年課税制度は、毎年110万円までの基礎控除がある通常の贈与税制度です。