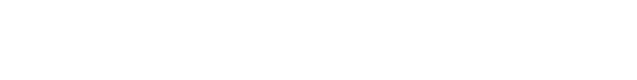目次
相続・遺言コラム
相続に関するタイムリミット(期限)
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士

はじめに
相続が開始してから、色々な場面でタイムリミット=期限が出てきます。
期限を過ぎると権利がなくなってしまうなど不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
死亡届は原則7日以内
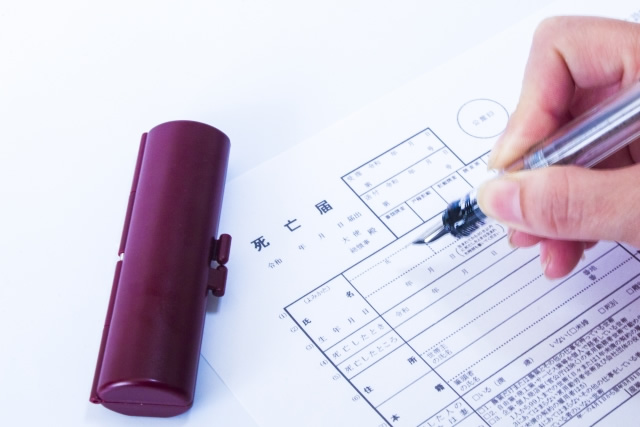
亡くなった方の親族や亡くなった方と一緒に暮らしていた方などは、死亡届を提出する義務があります。
提出期限は亡くなったことを知った日から7日以内です(戸籍法86条、87条)。
国外で亡くなったときには、確認手続きなどに時間がかかることから少し長めに設定されています。提出期限は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。
ここでポイントとなるのは、カウントが始まる日は、亡くなった日ではなく亡くなったことを「知った」日ということです。
遠方に住んでいる場合や疎遠になっていた場合などは、亡くなった日と亡くなったことを知った日にはズレが生じます。
亡くなったことを知ったのが亡くなった日から7日以上経過していたとしても、亡くなったことを知った日からカウントが始まりますので提出期限内に提出することができます。慌てずに手続きしてください。
正当な理由がないのに期間内に死亡届を提出しないときは、5万円以下の過料に処されてしまいます(戸籍法137条)。手続きの仕方や提出書類が分からなければ市役所などで教えてもらえますので、早めに手続きを始めましょう。
遺言書の検認は遅滞なく

亡くなった方から遺言書を預かっていた方は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく、家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。相続人が遺言書を見つけたときも、同じです(民法1004条)。
ここでの「遅滞なく」というのは、「直ちに」という意味に考えられています。
検認は、遺言書の現在の状態を保存してその後に偽造・変造されることを防ぐために行われる手続きなので、できるだけ早く行う必要があるからです。
検認を怠った場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります(民法1005条)。検認を行わずに遺言を執行したり、検認を行う前に遺言書を開封したりした場合も同じです。
遺言書の種類によっては探し方や見つけたときの対応が異なりますので、「遺言書の探し方と見つけたとき」をご覧ください。
相続放棄・限定承認は3か月以内

相続人になると、遺産を引き継ぐかどうか、意思を表明する必要があります。
選択肢は、単純承認・限定承認・相続放棄です。
それぞれの詳細は、「相続が発生したら行う手続きの流れ」や、「相続放棄とは?法的な効果や活用法、手続の仕方について」をご覧ください。
相続放棄と限定承認は裁判所に申し出なければ認められません。その期限は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。「自分が相続人であることを知った時」というのは、亡くなったことと、自分が相続人であることの両方を知った時です。
注意すべき点は、3か月間のカウントが始まる日が相続人ごとに異なる場合があるという点です。その場合、3か月間の期間満了日は相続人ごとに異なってきます。
例えば、先ほどの死亡届の例と同じように、亡くなった方と同居していた方と、遠方に住んでいたり疎遠になっていたりした方では、亡くなったことを知った日が違ってきます。また、当初から相続人であった方と、誰かが放棄の手続きをしたことによって相続人になった方では、自分が相続人であることを知った日が異なってきます。
「あの人がまだだから自分もまだに違いない」と思っていると限定承認・相続放棄の期間を過ぎてしまい、単純承認になってしまうことがあります。また、「あの人の期限が過ぎてしまっているのだから、私ももう無理だ」とは限りません。自分自身の申出期限をきちんと把握する必要があります。
長年疎遠だったので遺産の状況がわからず、承認するか放棄するか意思表示を決めかねる場合などは、家庭裁判所に申請すると期間を延長してもらえます。
また、3か月を過ぎてしまった場合については、「3か月過ぎてからの相続放棄ってできる?」をご覧ください。
遺留分侵害額請求は1年以内

遺留分は、一部の相続人に認められている、遺産の最低限の取り分のことです。
贈与や遺贈(遺言による贈与)によって遺留分が侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた人に対して、侵害された遺留分に相当するお金の支払いを請求(遺留分侵害額請求)することができます。
遺留分について詳しくは、「遺留分って何?」をご覧ください。
また、最近の民法改正によって「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に変わりました。その点について詳しく知りたい方は、「約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第4回)~遺留分制度、特別寄与料、持戻し免除の意思表示の推定規定について~」をご覧ください。
遺留分侵害額請求権は、亡くなったことと、自分の遺留分が侵害される内容の贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行わなければなりません(民法1048条)。1年を経過してしまうと、時効によって権利が消滅してしまいます。
また、亡くなったことや遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知らなかったとしても、亡くなってから10年を経過してしまうと、時効によってその権利が消滅してしまいます(民法1048条)。
遺留分侵害額請求権のポイントは、亡くなったことなどを知らなかったとしても、亡くなった時から10年を経過してしまうともう権利を行使することができないという点です。「知らなかった」という主張は通りませんので、注意する必要があります。
特別寄与料の請求は6か月以内
亡くなった方に対して、無償で療養看護などを行い、亡くなった方の財産の維持や増加に特別の寄与をした親族は、亡くなった後に相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することができます。
近年の民法改正によって新設された制度ですので、「法改正に対応 寄与分と特別寄与料について」や、「約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第4回)~遺留分制度、特別寄与料、持戻し免除の意思表示の推定規定について~」をご確認ください。
特別寄与料の請求は、亡くなったことと、誰が相続人であるのかということの両方を知った時から6か月以内に行わなければなりません。また、亡くなった時から1年以内という制限もあります(民法1050条第2項ただし書き)。
こちらも、遺留分侵害額請求権と同じく、期間をすぎると権利を行使することができなくなってしまいますので注意が必要です。
相続税の申告は10か月以内
相続税の申告にも期限があります。
相続税の申告が必要な方は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を税務署に提出する必要があります(相続税法27条1項)。
正当な理由がないのに期限内に申告書を提出しなかった場合には、無申告加算税や延滞税が課されるのみならず、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる場合があります(相続税法69条)。提出した申告書は、あとで金額を修正したりすることができますので(相続税法30条、31条など)、できるだけ早く手続きをすることが大切です。
わからない場合には税理士に相談してみてください。
不動産の登記の申請はこれから注意
2021年4月28日に、民法の一部などを改正する法律が公布されました。この改正法によって不動産登記法も改正され、相続で不動産を取得した方は一定期間内に登記を行わなければならないという規定が新設されました。
今回の改正法の適用日は、2024年4月1日です。
相続によって不動産の所有権を取得した方は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転登記をしなければなりません。遺産分割などによって所有権を取得した方だけでなく、遺贈によって不動産を取得した方も同様です(不動産登記法 新76条の2)。
正当な理由がないのに申請を怠ってしまうと、10万円以下の過料に処するという罰則規定もあります(不動産登記法 新164条)。
特別受益・寄与分の主張は原則として10年以内
特別受益は、亡くなった方から遺産の前渡しと言える贈与や遺贈(遺言による贈与)を受けた相続人がいる場合の、その特別な利益を言います。
一部の相続人だけが特別な利益を受けているのは不公平なので、その分を考慮して遺産分割することができます。
寄与分は、亡くなった方の財産について、生前に増加させたり、維持したりするような貢献をした相続人に認められる、特別な遺産の取り分を言います。
特別受益について詳しくは、「特別受益って何?仕組みや計算方法について」をご覧ください。
寄与分について詳しくは、「法改正に対応 寄与分と特別寄与料について」をご覧ください。
2023年4月1日に、民法等の一部を改正する法律が施行されました。
それにより、亡くなってから10年経過後は、原則として特別受益・寄与分の主張ができなくなりました(民法904条の3)。
つまり、亡くなってから10年経過した後は、法律で決められた割合で分ける「法定相続分による分割」か遺言により指定された割合で分ける「指定相続分による分割」で遺産分割することになります。
例外として、次の3つに当てはまると、亡くなってから10年経過していても、特別受益や寄与分を考慮した分け方(具体的相続分による遺産分割)をすることができます。
- 亡くなってから10年経過するよりも前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき
- 亡くなった時から10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合で、そのやむを得ない事由が消滅した時から6か月経過する前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
- 当事者全員の間で具体的相続分による遺産分割を実施する合意があるとき
この期限については、2023年4月1日以前に開始した相続についても適用されます。
遺産分割をする期限はありませんが、特別受益や寄与分について主張したい場合は、期限に気を付ける必要があります。
この改正については詳しくは、「遺産分割に期限ができた?!2023年4月から変わること」をご覧ください。
おわりに
身近な方が亡くなったときには、気持ちに余裕がない中で様々な手続きを期間内に行わなければなりません。
わからないことがあった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。