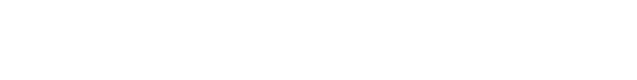相続・遺言コラム
相続人がいない?そんなときは相続財産清算人!
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士

相続人がいないって、どういうこと?

亡くなった方に遺産を引き継ぐ人がいない、ということがあります。
それは、
・身寄りがなく、法律で決まった遺産を引き継ぐ人がいない場合
・法律で決まった遺産を引き継ぐ人全員が、引き継ぐ権利を放棄する手続きをした場合
です。
身寄りがなく、法律で決まった遺産を引き継ぐ人がいない場合
亡くなった方の遺産を引き継ぐ人(法定相続人)は法律で決まっていて、配偶者(夫や妻)、子どもや孫、親や祖父母、兄弟姉妹や甥姪などです。そのため、ずっと独身で、既に両親・祖父母が亡くなっていて、一人っ子の方が亡くなった場合、引き継ぐ人がいないことになります。
ほかにも、一人っ子で、結婚はしたけれど子どもはいなくて、両親・祖父母、配偶者(夫や妻)が先に亡くなっている場合や、ずっと独身で、既に両親・祖父母、兄弟姉妹が亡くなっていて、甥姪がいない(兄弟姉妹に子どもがいない)場合なども考えられます。
ずっと独身の方や一人っ子の方が多くなってきたので、このようなケースも増えてくるかもしれません。
ちなみに、亡くなった方の内縁の夫・妻(事実婚の相手)やおじ・おば、いとこは、法律上、遺産を引き継ぐ権利がありません。生前、いくら献身的にお世話をしたからと言って、当然に遺産をもらえるわけではないのです。
法律上遺産を引き継ぐ権利がない方に遺産を渡したい場合は、生前贈与や遺言を検討しましょう。
法律で決まった遺産を引き継ぐ人全員が、引き継ぐ権利を放棄する手続きをした場合
また、亡くなった方の遺産が、預金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合、法定相続人全員が、遺産を一切放棄することがあります。
ほかにも、亡くなった方と生前疎遠で、関わり合いたくないという理由で放棄することもあります。
すると、亡くなった方の遺産を引き継ぐ人がいない、ということになります。
この、亡くなった方の遺産を一切引き継がない旨を家庭裁判所に申述する手続きのことを、相続放棄といいます。
遺産を引き継ぐ人が行方不明の場合は?
ところで、亡くなった方の戸籍を調べてみると子どもがいるようだが、行方不明で生きているかもわからない、という場合はどうなるでしょうか。
この場合、遺産を引き継ぐ人がいない、とまでは言えないので、相続財産清算人を選任することはなく、行方不明の子どもについて家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうか、失踪宣告の手続きをすることになります。
不在者財産管理人が選任された場合は、不在者財産管理人が行方不明の子どもの代わりに亡くなった方の遺産を引き継いで、行方不明の子どもが見つかるか、失踪宣告が確定するまで管理します。
行方不明の子どもの失踪宣告が確定した場合は、行方不明の子どもの相続が開始することになります。
すべて遺贈するという遺言があった場合は?
そして、法律で決まった遺産を引き継ぐ人はいないけれど、「私の遺産のすべてをAに遺贈する。」のような遺言(全部包括遺贈)があった場合、包括受遺者(遺言で遺産全部の贈与を受ける人)は相続人と同一の権利義務を持っていることになるため、相続財産清算人は選任されません。
相続人がいないと、何が問題?

相続人がいないと、亡くなった方の財産がそのままになってしまいます。
例えば、亡くなった方が不動産を持っていた場合、不動産の管理がなされず、荒れ放題になる可能性があります。生い茂った雑草をそのままにしては火災の心配がありますし、建物が傷んでしまうと倒壊の危険性が出てきます。
また、管理費や固定資産税などの費用が支払われないままになってしまいます。
さらに、亡くなった方と共有で不動産を所有していた場合、亡くなった方に相続人がいれば、相続人が亡くなった方の持分を引き継ぐことになります。しかし、亡くなった方に相続人がいないと、亡くなった方の持分が宙に浮いて、不動産を処分することができなくなります(自動的に存命の共有者に亡くなった方の持分が移行するわけではありません。)。
ほかにも、法定相続人ではないけれど、亡くなった方のお世話をしてきた方や、成年後見人など亡くなった方の財産を管理していた方は、預かっていた財産をどうしたらいいのか困ってしまいます。
さらに、亡くなった方にお金を貸していた方や、亡くなった方のために費用を立て替えて支払った方、遺言によって財産をもらうことになっている方は、誰に請求したらいいのかわからなくなってしまいます。
また、亡くなった方がマンションを持っていた場合、そのままになってしまうと未払い管理費がどんどん増えていくことになってしまいます。
このような問題がおこるため、「相続財産清算人」という制度があります。
なお、この制度は、2023年(令和5年)3月31日までは「相続財産管理人」という名称でした。しかし、相続人に財産を引き継げるようになるまで財産を管理する「相続財産管理人」と区別できるようにするため、名称変更されました。
また、2023年(令和5年)4月1日から「所有者不明土地・建物管理制度」が始まりました。
これは、土地や建物(マンションなどの区分所有建物は対象外です。)について、調査を尽くしても所有者がわからない、どこにいるのかわからないときに、利害関係者がその土地・建物の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てることにより、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうものです。
相続財産管理人は、不動産に限らず亡くなった方の財産すべてを管理・清算することになるので、手続きが煩雑です。
不動産登記簿上の所有者の法定相続人が全員放棄してしまった土地を購入したい場合や、その土地に雑草が繁茂していて困っている場合などには、「所有者不明土地・建物管理制度」の利用を検討することができます。
相続財産清算人
亡くなった方の財産を引き継ぐ人がいない場合、利害関係者などが家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることになります。
そして、家庭裁判所から選任された相続財産清算人が亡くなった方の財産を管理・清算し、相続人の捜索をします。
できること
相続財産清算人は、亡くなった方の財産を自由に処分できるわけではなく、「保存・管理・利用・改良」行為のみ認められています。
例えば、不動産の「相続財産」名義への変更登記や預貯金の払戻・解約は可能ですが、不動産の任意売却や永代供養料の支払いなどは、裁判所の許可を得ないとできません。
また、節目ごとに裁判所に財産目録や経過報告書を提出しなくてはいけません。
このように、亡くなった方の財産を自分のものにするなどの不正行為がないように、裁判所がチェックする制度になっています。
なお、相続財産清算人には、ほとんどの場合、弁護士や司法書士が選任されます。
選任申立てができるのは
ところで、相続財産清算人の選任申立てをすることができる利害関係者とは、どのような人でしょうか。
例えば、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)、相続債権者(そうぞくさいけんしゃ)、受遺者(じゅいしゃ)です。
特別縁故者
特別縁故者は、亡くなった方と生計を同じくしていた方、療養看護に努めていた方、その他特別の縁故があった方のことをいいます。
特別縁故者は、亡くなった方の財産が十分ある場合に、相続財産の全部または一部を分与してもらえる可能性があります。
後述しますが、決められた期間内に相続人ですと名乗り出る人がいなくて、亡くなった方の借金をすべて支払った後、家庭裁判所に相続財産分与の申立てをして、家庭裁判所に相当であると認めてもらえば、残っている財産の全部または一部をもらえます。もらえる金額は、家庭裁判所が決めます。
なお、家庭裁判所に相続財産分与の申立てをしても、特別縁故者と認められない場合もあります。
例えば、生前仲の良かったお友達とか、亡くなった方のお葬式を行っただけの方などは、認められないでしょう。
亡くなった方と生計を同じくしていた方というのは、亡くなった方と一緒に生活していた内縁の配偶者(事実婚の相手)や配偶者(夫または妻)の連れ子(継子)など、亡くなった方と戸籍上のつながりはなくても、家族として一緒に生活していた方のことです。
療養監護に努めていた方というのは、親族としての扶養義務を超える程度、献身的に亡くなった方のお世話をしていた方のことです。親族以外でも認められることはありますが、職業的に報酬を受け取ってお世話をしていた場合は、その報酬以上に献身的に尽くしていたという特別の事情があれば、例外的に認められることがあります。
そのほか、特別縁故者と認められた例として、次のようなものがあります。
- 自宅にこもりがちで対外的な交際が難しかったため、代わりに自宅の害虫駆除作業や修理等を行い、民生委員や近隣と連絡を取って、緊急連絡先として自身の連絡先を伝え、時々安否確認をしていたいとこ
- 50年以上交流し、近隣に住み、亡くなる際には肉親以上のお世話を続け、死に水をとった元教え子
- 身寄りがまったくいず、孤独な生活だったところ、親子のような親密な交際をし、亡くなるまで3日ごとに訪問して話し相手になっていた友人
家庭裁判所に相続財産分与の申立てをする際には、自分が特別縁故者であることを裏付けるような証拠書類を添付するようにしましょう。
例えば、特別縁故関係について自分で詳しく書いた陳述書や亡くなった方と一緒に撮影した写真、手紙やはがき、メールなど交流がわかる資料などです。
相続債権者
相続債権者は、亡くなった方にお金を貸していた貸主や未払い家賃を請求していた大家さん、亡くなった方のために費用を立て替えて支払った方など、亡くなった方にお金を請求できる権利を持っている方のことです。
なお、葬式の費用は、通常喪主が負担するものとされているので、当然には立て替え費用とはなりません。
相続債権者は、亡くなった方の財産がある場合に、請求額の全部または一部を返済してもらえますが、亡くなった方の財産が借金ばかりだと、返済してもらえないばかりか、申立ての費用を負担することになるので、気をつける必要があります。
返済してもらえる金額は、亡くなった方の財産と借金の額、相続財産清算人の報酬や実費(相続財産清算人が任務を遂行するにあたって支払う経費)によって決まります。
例えば、亡くなった方の財産が1000万円あって、債権者が1人、請求額が500万円だった場合、相続財産清算人の報酬・実費が500万円以下であれば、全額の500万円支払われる可能性があります。
一方、亡くなった方の財産が1000万円あって、債権者が5人、請求額の合計が1000万円だった場合、相続財産清算人の報酬・実費を差引いた残額を債権者に配当されることになります。
そして、亡くなった方の財産が0円またはマイナス(借金)だけだった場合、残念ながら債権者は1円も回収することができずに終わります。
受遺者
受遺者は、亡くなった方が遺言で財産をあげると指定している方のことです。
受遺者は、相続債権者への返済後に財産が残っている場合に、支払いを受けることができます。
相続債権者への返済が優先されるので、遺言に書かれているとおりの財産がもらえるとは限りません。
ちなみに、遺言に財産をあげると書いてあっても、「もらいません。」と断ることもできます。
申立てにかかる費用
裁判所に申立てするときにかかる費用は、次のとおりです。
- 収入印紙(申立書に貼ります) 800円
- 郵便切手(裁判所が連絡用に使います) 約1200円(裁判所によって違います)
- 官報公告費用(裁判所が官報に通知を載せる費用です) 5075円
上記のほか、亡くなった方の財産が十分でない場合、申立人が相続財産清算人の報酬や任務に必要な経費分の担保(予納金)としてあらかじめ裁判所に納付することがあります。
金額は、事案によって異なり、裁判官が決めます。
亡くなった方の財産を清算して、十分に預貯金の形で管理されるようになったら優先的に返還されますが、返還されないこともありますので、気をつけましょう。
申立てに関しては、裁判所のホームページをご覧ください。
清算業務の流れ
-
申立てを受けて、家庭裁判所が、相続財産清算人を選任します。
そして、選任されたことを知らせ、相続人は6か月以上の期間内に名乗り出るよう促す公告をします。この期間内に名乗り出る人がいないと、相続人がいないことが確定します。
(公告とは、広く一般に知らせることをいい、官報という国の機関紙や裁判所の掲示板に貼り出すことなどによって、全国民が認知した、ことにする制度です。) -
相続財産清算人は、亡くなった方の財産を調べます。
申立てをしたのが亡くなった方の成年後見人だった場合は、管理していた財産を引き継ぎます。
放棄の手続きをした親族がいる場合は、亡くなった方の生活歴や財産等について聞き取ります。亡くなった方の住居に伺って、通帳や有価証券、保険証券、借金の契約書などがないか、調査することもあります。
そして、財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。不動産の登記名義を「亡〇〇〇(亡くなった方の名前)相続財産」と変更し、預貯金は解約して相続財産清算人名義口座にまとめるなど、管理します(不動産は、最終的には裁判所の許可を得て売却などして、お金に換えます。)。
また、公告によって、亡くなった方が負っていた借金の貸主(債権者)や、遺言で贈与を受ける人(受遺者)を探すとともに、既に判明している債権者に対して請求を申し出るように催告します。
- プラスの財産が多い場合は、債権者や受遺者に支払いをしますが、マイナスの財産が多い場合は、相続財産清算人の報酬を裁判所に決めてもらい、任務でかかった経費と報酬を差引いた残額を債権者に配当して、裁判所に終了報告をします。
- 相続人が期限内に名乗り出ない場合で、亡くなった方と生計を同じくしていた方、療養看護に努めていた方、その他特別の縁故があった方(特別縁故者)の請求があるときは、家庭裁判所の審判にしたがってその方に財産の全部または一部を渡すことができます。特別縁故者が家庭裁判所に相続財産分与の申立てできるのは、相続人が名乗り出る期間が満了してから3か月以内です。
- それでもなお、財産が残っているときは、国庫に入れ、裁判所に終了報告をします。
相続財産清算人は、債権者や受遺者からの求めに応じて、相続財産の状況を報告する義務があります。
まとめ
亡くなった方に身寄りがない場合、親族がみんな放棄の手続きをとった場合、亡くなった方の遺産を引き継ぐ人がいない状態になってしまいます。
遺産に不動産があると、適切な管理がされず、近隣に迷惑をかける可能性があります。
また、亡くなった方に借金や未払金があると、債権者は誰に請求したらいいのかわからず、困ってしまいます。
このように、亡くなった方の遺産を引き継ぐ人がいない場合に、遺産を管理・清算する役割を担うのが、相続財産清算人です。
亡くなった方の遺産をお金に換えて、借金の返済や受遺者への支払い、清算人の報酬・実費に充てます。
特別縁故者は、期間内に家庭裁判所に申立てて、認められれば、家庭裁判所が決めた金額をもらえます。
それでもなお、財産が残っているときは、国に納めます。
特別縁故者、相続債権者、受遺者などの利害関係人は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立てをすることができますが、亡くなった方の遺産の内容によっては費用倒れになる可能性がありますので、気を付けましょう。
相続、遺産分割についてわからないことや心配なことがありましたら、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。