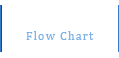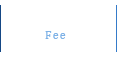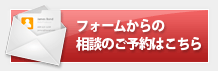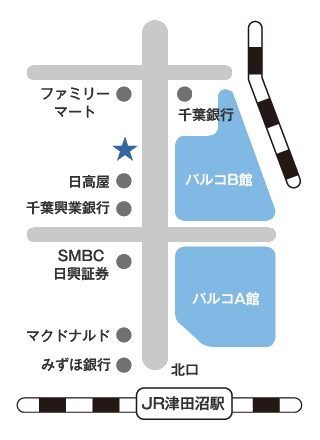債権法改正のポイントを徹底解説(第1回)~法定利率と債務不履行責任について~
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士
債権法とは、民法のうち、契約など取引関係に関するルールを定めた規定をいいます。
1896年の民法制定以来、債権法と呼ばれる部分については大きな改正がほとんど行われていませんでした。
このため、現代社会や経済情勢の変化に対応するべく債権法改正の検討が続けられ、2017年5月に債権法の改正法が成立しました。この改正法は、一部の規定をのぞき2020年4月1日から施行されています。
今回改正されたのは、民法第3編「債権」の規定及び「債権」の規定とかかわりのある第1編「総則」の一部規定です。
このうち、民法第1編「総則」に関しては、別の記事において詳細に解説することとし、本稿では民法第3編「債権」の規定に関する改正事項を解説します。
もっとも、第3編「債権」の規定の改正箇所は、取引関係において頻繁に適用される主要な条文だけでも以下のとおり多岐に渡ります。
- 法定利率に関する改正(404条)
- 債務不履行責任に関する改正(412条~422条の2)
- 詐害行為取消権に関する改正(424条~426条)
- 保証に関する改正(448条~465条の10)
- 債権譲渡に関する改正(466条~469条)
- 債務引受に関する改正(470条~472条の4)
- 定型約款に関する改正(548条の2~548条の4)
- 売買に関する改正(557条~581条)
- 消費貸借に関する改正(587条~591条)
- 賃貸借に関する改正(601条~622条の2)
- 請負に関する改正(634条~642条)
そこで、複数回に分けて、第3編「債権」の規定に関する改正事項を解説します。
第1回目となる今回は、法定利率に関する改正と、取引関係にある一方が契約違反をした場合の債務不履行責任に関する改正について解説します。
法定利率に関する改正

利息や遅延損害金については、当事者間の合意で利率を定めることができます。これを約定利率といいます。
当事者間で約定利率を定めなかった場合には、民法で定められた法定利率が適用されます。
また、取引関係等一定の場合には、商法に規定された商事法定利率が適用されていました。
市中金利と法定利率の乖離
改正前の民法では、法定利率は年5%と定められていました。
また、商事法定利率は年6%と規定されていました。
民事法定利率の年5%という利率は、民法制定当初の市中金利にあわせたものでした。
しかし、民法制定から120年が経過し、市中金利は年5%を大きく下回る状況が長期的に継続しています。
法定利率が市中金利を大きく上回ると、債務者が支払う遅延損害金や利息額が著しく多額となり、不公平が生じます。
また、交通事故等で被害者遺族に支払われる逸失利益の金額が低く抑えられてしまい、被害者遺族に酷となってしまいます。
これは、なぜかというと、中間利息控除というものがあるからです。
逸失利益のように、将来発生する損害を前もって賠償してもらうときに、今受け取ったお金を将来までの間に運用して得られる予定の利息分を、受け取る金額からあらかじめ引いておく、という考えです。
この「得られる予定の利息」の計算に法定利率が適用されるため、法定利率が高いほど、被害者遺族が受け取れる金額が低くなってしまうのです。
このような不公平をなくすために、法定利率の見直しが行われました。
法定利率は変動制へ

改正によって、法定利率は年3%となりました(404条第2項)。
また、年6%と定められていた商事法定利率は廃止され、民法に定める法定利率に統一されました。
さらに、この法定利率は市中金利の変動にあわせて3年ごとに見直しをするという変動制が導入されました。
施行後3年ごとに、以下のような方法で見直しがなされます。
まず、日本銀行が公表している過去5年間における短期貸付の1か月あたりの平均利率を合計します。
そして、この合計額を60(5年×12か月)で割って、1か月あたりの短期貸付の平均利率を出します。
この平均利率を基準割合とします。
この基準割合と、前回の法定利率の変動時の基準割合とを比較して、1%以上の変動があった場合に、1%刻みで法定利率を増減します。
今回の改正法は2020年4月に施行されたので、法定利率の見直しが行われるのは2023年4月です。
法定利率が変動するのかしないのか、また、変動するとして上がるのか下がるのかによって、金額が大きく変化する場合があります。2023年4月の見直しの際には注意が必要です。
債務不履行責任に関する改正

債務不履行責任とは、契約関係にある当事者の一方が契約上の債務を契約通りに履行しなかった場合に、もう一方の当事者が債務不履行をした当事者に対して追及することのできる責任です。
例えば、自動車の売買契約の場合、売主(Aさん)は買主(Bさん)に自動車を引渡す債務があり、買主(Bさん)は売主(Aさん)にお金を支払う債務があります。
AさんがBさんからお金を受け取ったのに、Bさんに自動車を引き渡さなかったときは、BさんはAさんに対して債務不履行責任を問える、ということです。
債務不履行には、いくつかのパターンがあります。
- 履行不能
「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるとき」を言います。
債権者は、債務の履行を請求できませんが、契約成立時に履行不能だったときは、損害賠償請求できます。 - 履行遅滞
契約で決められた期限までに債務を履行しないことです。
例えば、上記の例でいえば、BさんがAさんに期限までにお金を支払わない場合です。 - 不完全履行
契約で決められた債務を履行したけれど、内容が不完全であることです。
例えば、上記の例でいえば、AさんがBさんに引き渡した自動車の仕様が契約と違った場合です。
損害賠償責任の要件の明文化
契約の相手方が債務不履行をした場合に、もう一方の当事者は相手方に対して損害賠償を請求することができます。
今回改正があったのは、債務不履行に基づき損賠賠償請求をするための要件です。
改正前の債権法では、債務を契約通りに履行することができなくなった場合(これを「履行不能」といいます)に限って、債務不履行に基づく責任を追及するために債務者の「責めに帰すべき事由」(帰責事由)が必要であることが定められていました。
他方、契約で定めた履行期に遅れて債務を履行した場合(これを「履行遅滞」といいます)など、他の債務不履行の類型に関しては、帰責事由が要件となるのか条文上は明らかではありませんでした。
この点について、債権法改正前の判例は、履行遅滞であっても履行不能と同様に、債務不履行責任を追及するための要件として債務者の帰責事由が必要であると判断していました。
このように、改正前の債権法は、条文の不明確な点を判例によって補っている状態でした。
そのため、改正法は、原則として債務不履行が発生した場合には損害賠償請求ができるとして、履行遅滞も履行不能と同様に扱うことを条文に明確に定めました(415条第1項)。
さらに、改正法は、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」がある場合には、債務者は免責されることとしています。
この免責事由は、従来の帰責事由の解釈を踏襲するものです(415条第1項ただし書き)。
契約解除の要件の明文化

改正前の債権法は、契約の解除を、損害賠償請求と同じように、債務を履行しない相手に対する「責任追及のための手段」の1つとして位置付けていました。
このことは、債務不履行に基づく契約解除をする場合にも、損害賠償請求と同様に債務者の帰責事由が要件になると考えられていたことに表れています。
これに対して、契約解除をそのような責任追及のための手段として捉えるのではなく、契約当事者がその契約による拘束から解放されるための手段として捉えるべきではないかとの意見が主張されていました。
そこで改正法は、契約の相手方の債務不履行に基づき契約を解除する場合には、債務者の帰責事由を要しないこととしました(540条第1項)。
この点は、従来の実務上の運用を変更するものといえますので、注意が必要です。
なお、債務不履行による解除には、「催告解除」(541条)と「無催告解除」(542条)という2つの方法があります。
催告解除とは、一定の期間を定めて相手方に債務の履行を請求し(このような請求を「催告」といいます)、その期間内に履行がされない場合に初めて解除ができるという方法です。
つまり、契約を解除する前に、相手方への催告と一定期間の経過が必要であり、すぐに契約を解除することはできません。
これに対して、催告をせずにただちに契約を解除することができるのが「無催告解除」です。
催告なく突然契約を解除されると相手方に不利益が生じてしまう場合がありますので、催告解除が原則です。
無催告解除ができる場合は改正によって明文で規定されましたので、この後確認をします。
先に簡単に説明すると、催告解除と無催告解除の区別は、契約の目的を達成する可能性の有無が基準となります。
つまり、債務の不履行があっても催告をして履行されれば契約の目的を達成することができるのであれば、催告が必要になります。
例えば、新車を購入したのに、販売所が納入日になっても新車を納入してくれないような場合が挙げられます。
これに対して、催告をしてももはや契約の目的を達成することができないことが明らかであれば、催告は必要ありません。
例えば、コンビニが洋菓子製造会社にクリスマスケーキを発注していたのに、24日になっても納品されないような場合が考えられます。クリスマスケーキはクリスマスに販売するものなので、24日に納品されなければもはや契約の目的を達成することができません。
このような「契約の目的を達成する可能性」という考え方は、改正法において「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」には解除を認めないとする規定にも表れています(541条ただし書き)。
不履行が軽微であるならば契約の目的が達成できていないとはいえないため、たとえ催告をしたとしても契約を解除することはできないのです。
不履行が軽微な場合に解除することができないという規定は、従来の判例の考え方を明文化したものです。
したがって、催告解除に関する実務上の運用はこれまでと大きく変わるものではありません。
他方、無催告解除に関しては、改正法で解除の対象となるケースが以下のとおり具体的に定められました。
- 債務の全部の履行が不能であるとき
- 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
- 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
- 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
- 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
5つの場合が規定されていますが、これらは、催告をしてももはや契約の目的を達成することができない、あるいは、契約の目的を達成する可能性が極めて低い場合です。
このような場合には、損害の発生を最小限に抑えるために、また、新たな取引の相手方を見つけるためにも、契約当事者を早期にその契約から解放させる必要があります。
そのため、無催告解除が認められるのです。
例えば、無催告解除ができる場合の2つ目は、債務は履行できるものの、債務者が明確に全部の履行を拒絶する意思表示をしている場合です。
改正法によってこのような場合に無催告解除ができることになったので、相手が、債務の履行ができるにもかかわらず履行を拒絶し、それなのに合意解約にも応じようとしないような場合に、債権者が迅速に解除することができるようになりました。
このような場合に債権者をその契約から早期に解放することによって、債権者としては早期に新たな取引先を探しやすくなり、債務不履行による損害の発生を最小限に抑えることが可能となるでしょう。
まとめ
法定利率は、今後定期的に見直しがなされるなど大きな変化があったといえます。
債務不履行責任は、従来の実務や判例の判断が反映されている部分が多く、それほど大きな変更があったわけではありませんが、従来曖昧であったことが明文で規定されたり新たな言葉が用いられたりしているので、不安なことやわからないことがあったら弁護士にご相談ください。