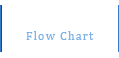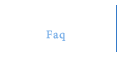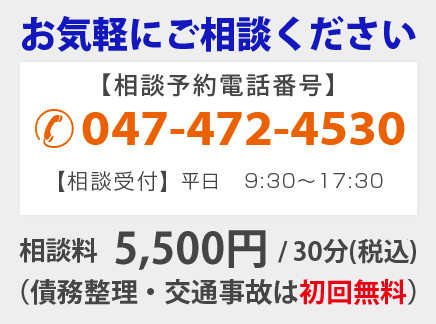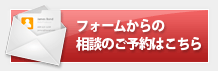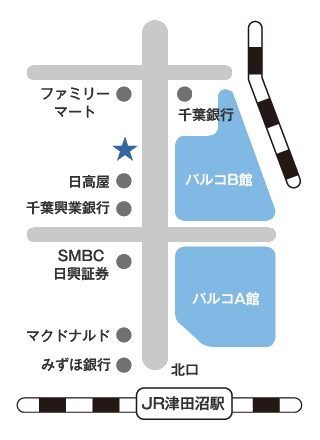劇場型投資詐欺の手口と被害防止策!うまい話に潜む危険
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士

目次
劇場型投資詐欺が急増中!あなたも狙われているかもしれません
近年、「劇場型」と呼ばれる投資詐欺の被害が急増しています。金融庁が公表している2024年10月1日~同年12月31日の「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等によると、12,432件の相談のうち、詐欺的な投資勧誘に関するものが1,641件で、そのうち1,406件が何らかの被害があったそうです。
この「劇場型」という名称は、複数の人物が役割を分担して被害者を騙す手口に由来します。未公開株や社債を発行する企業の従業員、それを高値で買い取る証券会社の社員などに成りすました人物が次々と登場し、まるで演劇のように巧妙なシナリオで被害者を誘導していきます。
本記事では、私たち牧野法律事務所で実際に扱った事件をもとに、劇場型投資詐欺の典型的な手口、最新の傾向、そして被害に遭わないための具体的な対策をご紹介します。また、被害に遭ってしまったときの対処方法も最後に記載しました。あなたの大切な資産を守るために、ぜひ最後までお読みください。
※本記事で紹介する事例は、個人情報保護のため会社名や住所などを変更しています。
劇場型投資詐欺とは?基本的な仕組みと特徴
劇場型投資詐欺は、複数の詐欺師が異なる役割を演じ、被害者を信用させて金銭をだまし取る手口です。その基本的な仕組みと特徴を理解しておくことが、被害防止の第一歩となります。
劇場型投資詐欺の典型的な流れ
1. 勧誘の電話
有望な未公開株や社債の購入を勧める電話がかかってくる
2. 別の関係者からの連絡
数日後、別の金融機関を名乗る人物から「高値で買い取りたい」との連絡がある
3. 信頼性の演出
公的機関との関わりや地元出身の経営者などを強調し信頼感を高める
4. 急がせる戦略
「期間限定」「数量限定」などと焦らせて冷静な判断を妨げる
5. 振込要請
最終的に指定口座への振込を要求する
劇場型投資詐欺の特徴
複数の登場人物
企業担当者、証券会社社員、金融アドバイザーなど複数の役割を演じ分ける
実在する企業名の悪用
大手企業の名前に似た社名を使用し、正当性を装う
高い利回りの提示
現実離れした高い利回り(年10〜20%以上)を約束する
希少性の強調
「あなただけに特別に」「限定募集」などの言葉で特別感を演出する
洗練された資料
パンフレットやウェブサイトなど、見た目には本物そっくりの資料を用意する
劇場型投資詐欺の最大の特徴は、複数の人物が異なる立場から連絡してくることで信頼性を高める点です。「別々の会社から連絡が来たのだから本物だろう」という心理を巧みに利用しています。
実際の投資詐欺事例:Aさんの1,000万円被害ケース
ここでは、当事務所が実際に扱った劇場型投資詐欺の事例をご紹介します。この事例は投資詐欺の典型的な手口と被害回復の難しさを示しています。
Aさんのケース:退職金1,000万円を失った被害者
Aさんは定年退職して妻と2人暮らしの60代男性です。長年勤めた会社を退職し、退職金を含む貯蓄でゆとりある老後を過ごす予定でした。
詐欺の始まり:最初の電話

ある日、千葉県船橋市にあるAさんの自宅に、「四井角共アセットマネジメント」の田貫と名乗る人物から電話がありました。田貫は「おたくは株式会社アースキットの転換社債をお持ちではないですか」と尋ねてきました。
Aさんが「持っていない」と答えると、田貫は次のように説明しました:
「株式会社アースキットはレアメタルの開発を行っており、経済産業省からも援助を受けています。このたび、ハワイ沖でレアメタル採掘を行うことになり、その資金を得るため、転換社債を発行することになりました。
アースキットの社長は船橋市〇〇町の出身なので、〇〇町の方に優先的に発行することになりました。」
そして「もし社債をお持ちでしたら、額面の2.5倍で買い取ります」と持ち掛けてきました。
詐欺の展開:二人目の登場人物

翌日、今度は「オリエント信託」の亜久井なる人物から同じような電話があり、亜久井は「うちは3.8倍で引き取ります」と言ってきました。
Aさんは、アースキットという会社は聞いたこともありませんでしたが、大手銀行の系列会社らしきところから続けて電話がかかってきたため、すっかり信じ込んでしまいました。
詐欺の完成:お金の振込み

数日後、Aさんの自宅にアースキットのパンフレットが届きました。Aさんがパンフレットに記載されていた番号に電話をかけると、担当者から「2年ものの社債だと、年利18%になりますよ」と勧められました。
高利回りに魅力を感じたAさんは、1,000万円を指定された銀行の口座に振り込みました。
被害の発覚と回復の難しさ

しかし、銀行が不審に思い、アースキットの口座は凍結されました。Aさんは田貫や亜久井、アースキットに電話をかけましたが、どの電話も「現在使われておりません」となっていました。
Aさんの依頼を受け、当事務所がすぐに口座の仮差押えを行いましたが、他にも被害者が多数おり、配当を求めてきたため、最終的にAさんの手元に戻ったのは100万円余りでした。
このケースから学べる教訓
- 知らない会社からの突然の連絡には警戒する
- 複数の会社から連絡があっても、それが詐欺の手口である可能性を疑う
- 年利18%という非現実的な高利回りを約束する投資話は疑ってかかる
- 地元の繋がりを強調する話には要注意
- 振込前に必ず第三者(家族・弁護士など)に相談する
劇場型投資詐欺の最新手口
2025年最新の手口
劇場型投資詐欺の手口は年々巧妙化しています。最近の調査によると、以下のような新たな傾向が見られます:
1. SNSを活用した勧誘
InstagramやXなどのSNSで「投資の成功者」を装って接触し、詐欺に誘導
2. 環境・SDGs関連投資
カーボンニュートラルやSDGs関連の投資と称し、社会貢献性をアピール
3. AI・量子コンピュータ関連企業
最新技術を持つスタートアップへの投資と称して資金を募る
4. メタバース・仮想空間の土地取引
デジタル資産の価値高騰を煽り、投資を促す
5. 海外不動産投資の仲介
実在しない海外物件への投資を持ちかける
急増中のSNS型投資詐欺
従来の劇場型投資詐欺は、主に電話を利用して接触してきました。現在は、SNSを利用した詐欺が急増しています。
インターネット上に著名人の名前や写真を無断使用した広告で、「有名投資家が直接指導します」「必ずもうかる」「絶対に損しない」などと投資に誘う。
マッチングアプリで接触してきて、投資に誘う。
いずれも、SNSに誘導して、次のような流れでお金をだまし取ります。
1.投資セミナーのグループに招待される
共犯者が「わたしも〇〇先生のおかげで100万円もうかりました」「がんばれば、たくさんブランド品を買えるようになれますよ」など安心させ、投資を勧める
2.投資家やそのアシスタントから振込指示
投資用アプリや投資用サイトに誘導され、 「最初の投資として、指定する口座に10万円振り込んでください」と指示される
3.偽のアプリ(サイト)で利益が出ているように見せる
アプリ(サイト)で本当に利益が出ているように見せて安心させる。利益の一部を被害者口座へ振り込みして、「いつでも引き出せる」と思わせることもある
4.さらに高額の投資を勧める
「もっと大きな利益を出すためには、もっと大きな金額が必要」「今なら好条件で融資します」とさらに投資を勧める
5.資金を引き出すための手数料を要求
利益を取り出したいと言うと、「手数料が必要なので、100万円振り込んでください」「税金として100万円支払わないと出金できません」と要求する
6.連絡が取れなくなる
「おかしい」と詐欺に気づいたときには、連絡が取れなくなっている
従来の電話での詐欺は、主に60代以上の男性がターゲットになっていたようですが、最近のSNSを利用した詐欺は、男女ともに10代~80代の幅広い年代の方が被害に遭っています。「自分は騙されない」と思っている方ほど注意が必要です。
被害に遭わないための4つの対策
うまい話はないと肝に銘じる
投資詐欺に遭わないための鉄則は、「うまい話はない」。これに尽きます。
投資には必ずリスクが伴います。ハイリターンを得ようとすれば、それに見合ったリスクを取らなければなりません。「確実に儲かる」「リスクなしで高利回り」などという話は、100%詐欺と考えるべきです。
Aさんの事例でいえば、いまのご時世「年利18%」などありえないことは落ち着いて考えればわかることです。また、社債を買った人がいるかどうか、町中の世帯に行き当たりばったり電話をかけて調べるなど、時間やコストを考えれば商業的に合理的ではありません。
具体的なチェックポイント:
- 年利5%以上の利回りを約束する話は要注意
- 「必ず儲かる」「損はしない」という説明には警戒
- 「今だけ」「あなただけ」「特別に」という言葉に惑わされない
本物の金融業者かどうか確認する
本件では実在の銀行や証券会社の系列だと誤認させるような名称が使われていました。いまはインターネットで簡単に検索できるので、その会社が本当に実在するのかを確認しましょう。
不特定多数の投資を勧誘することができるのは、金融庁(財務局)に登録された業者に限られます。未登録の業者が勧誘するのは、金融商品取引法に違反します。
確認方法:
1. 金融庁のホームページで業者検索
2. 日本証券業協会の会員検索
日本証券業協会:協会員名簿
3. 投資信託協会の正会員一覧
投資信託協会:正会員一覧
また、仮に実在したとしても、名前を騙っている可能性もあるので、念のため電話して確認すべきです(もちろん公式ホームページや電話帳に載っている番号にかけましょう)。
勧誘の手口を知り、冷静に判断する
詐欺師は人間の心理的弱点を巧みに突いてきます。代表的な手口を知り、冷静に対処することが重要です。
詐欺師がよく使う心理テクニック:
1. 希少性の演出
「限定〇名様のみ」「期間限定」などと焦らせる
2. 権威性の利用
「大手企業との提携」「政府機関のお墨付き」などと強調
3. 社会的証明
「多くの人が既に投資している」「〇〇さんも購入した」と同調圧力をかける
4. 返報性の原理
小さな特典や情報を与え、お返しに投資を促す
5. 一貫性の原理
小さな約束から徐々に大きな決断へと誘導する
これらの手口に対抗するには、「24時間考える時間をください」と伝え、その間に冷静に判断することが効果的です。
怪しいと思ったらすぐに相談する
いままで扱った事件の中には、被害者の方は「怪しい」と感じながらも、ずるずると詐欺的な取引に引きずり込まれていくというケースが多くあります。
詐欺グループは人間の心理をよく研究しているので、一人だとそのからくりになかなか気づくことができません。
相手から「未公開株」「新規公開株」「必ずもうかる」などの言葉が出てきたら、「怪しい」と警戒しましょう。
そして、怪しいと思ったら、必ず家族や友人、弁護士、各機関に相談しましょう。客観的な視点から見ることで、詐欺の兆候に気づきやすくなります。
- 消費者ホットライン:188(いやや)
- 金融庁の詐欺的な投資に関する相談ダイヤル:0570-050-588
- 金融庁の金融サービス利用者相談室ウェブサイト受付窓口:インターネット情報受付窓口:金融庁
- 警察相談専用窓口:#9110
- 日本証券業協会の「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター:0120-344-999
- 最寄りの弁護士会の法律相談窓口
金融庁も詐欺的な投資勧誘等についての注意喚起をしており、投資詐欺被害防止特設ページでは最新の手口や対処法が紹介されています。
投資詐欺の被害に遭ってしまったら
万が一、投資詐欺の被害に遭ってしまった場合は、以下の対応を迅速に行いましょう:
1. すぐに警察に被害届を提出する
- 詐欺の証拠となる資料(パンフレット、メール、録音など)を保存する
- 振込先の口座情報を正確に伝える
2. 金融機関に連絡し、振込取消を依頼する
- 振込直後であれば、取消できる可能性がある
- 24時間以内の対応が重要
3. 弁護士に相談し、法的措置を検討する
- 口座凍結のための仮差押え申立て
- 詐欺グループへの損害賠償請求
- 刑事告訴のサポート
4. 消費者センターに相談する
- 類似被害の情報共有
- 専門家による無料相談の利用
被害金の回収は容易ではありませんが、早期対応によって被害を最小限に抑えられる可能性があります。特に振込直後の対応が重要です。
まとめ:自分の身は自分で守る
劇場型投資詐欺は年々巧妙化しており、誰もが被害に遭う可能性があります。以下のポイントを常に心がけ、自分の資産を守りましょう。
- 「うまい話はない」という原則を忘れない
- 正規の金融業者か確認する
- 高利回りを約束する投資話は疑ってかかる
- 判断を急がず、第三者に相談する
- 少しでも怪しいと思ったら専門家に相談する
自分は大丈夫だと過信せず、常に警戒心を持つことが最大の防御策です。高齢者の方や投資初心者の方は特に注意が必要です。ご家族や周囲の方々にも、この記事の情報を共有していただければ幸いです。
少しでも不安や疑問がある場合は、お気軽にご相談ください。