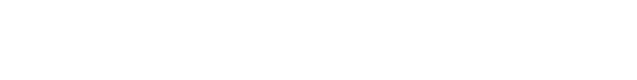相続・遺言コラム
約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第4回)~遺留分制度、特別寄与料、持戻し免除の意思表示の推定規定について~
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士

2019年7月1日に多くの規定が施行された相続法について、改正の背景についてはすでに当事務所のコラム「約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第1回)~改正の背景について~ 」で解説をしました。
また、改正の内容については、自筆証書遺言制度の見直しと配偶者居住権制度の創設については「約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第2回)~自筆証書遺言制度、配偶者居住権制度について~ 」で解説を行いました。さらに、遺産分割制度と相続の効力等については「約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第3回)~遺産分割制度、相続の効力等について~」で解説をしました。
今回は最終回として、以下の3つの改正について解説します。
- 遺留分制度に関する見直し
- 相続人以外の者の貢献を考慮する特別寄与料の創設
- 夫婦間の不動産贈与における持戻し免除の意思表示の推定規定の創設
遺留分制度に関する見直し
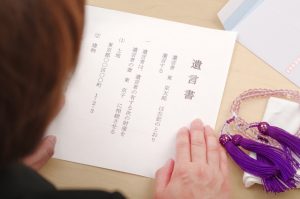
遺留分とは、亡くなった方の意思にかかわらず一定の遺産の分配を相続人に保障する制度です。
例えば、亡くなった父親が遺言で、全財産を愛人に贈与するとした場合でも、子どもが遺留分に関する権利を行使すれば亡くなった父親の遺産の一部を取得することができます。
なお、遺留分について詳しくは、「遺留分って何?」をご覧ください。
改正前の遺留分制度の問題点
改正前は、この相続人による遺留分に関する権利行使を遺留分減殺請求といいました。
遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈(遺言による贈与)・生前贈与は、侵害する範囲で失効して、対象となった不動産や有価証券等などの財産が減殺請求者との共有関係になる効果がありました。そして、例外的に、現物返還の代わりにお金で弁償することも許されるとされていました。
そのため、次のような問題点が指摘されていました。
- 遺産分割の長期化
遺留分減殺請求によって現物返還を求められると、遺産分割自体がストップし、遺産分割手続きが複雑化して、解決まで数年を要することも珍しくありませんでした。 - 共有関係の発生
遺留分減殺請求によって不動産が共有状態になると、その後の管理や処分が困難になる問題がありました。 - 事業承継への悪影響
事業用財産が減殺請求の対象となると、事業の継続に支障をきたす恐れがありました。
改正後→遺留分侵害額請求権
改正法では、従前の「現物返還」を求める遺留分減殺請求権から、「金銭給付」を求める「遺留分侵害額請求権」という金銭債権に変更されました。
この結果、相続人によって遺留分侵害額請求権が行使されたとしても遺産分割手続自体には影響を生じず、権利行使をした相続人に対しては金銭の支払いのみがなされることになります。
そして、請求を受けた受遺者または受贈者がすぐに支払えないときは、裁判所に対して、相当の期限を設けることを認めてもらうように求めることができるようになりました。
今回の改正によって、相続争いが長期化する要因の1つが解消されたということです。
遺留分算定の基礎財産
各自の遺留分を計算するための額は、改正前後で変わりません。
遺留分を計算するための財産の額=亡くなった時点の財産の額
+贈与した額
-亡くなった方の債務の額
変わった点は、「贈与した額」の部分です。以下のように、相続人に対する贈与と第三者に対する贈与を明確に区別し、対象となる贈与を限定することになりました。
相続人に対する生前贈与の額:特別受益に該当する贈与で、原則亡くなる10年以内の贈与の額
※特別受益に該当:結婚、養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与
なお、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、亡くなる1年前(相続人の場合は10年前)よりも過去の贈与でも、対象となる点は改正前と同様です。
具体的な事例での比較
私の遺留分侵害額は、次のとおり1000万円になります。
(500万円+3500万円)×1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分)=1000万円
改正前:減殺請求
贈与と遺贈の減殺の順序は、遺贈が先のため、第三者Aに対して、船橋市の土地(500万円分)の減殺、兄に対して習志野市の土地の持ち分7分の1(=500万円/3500万円)(500万円分)の減殺をそれぞれ求めることができます。
兄と習志野市の土地を共有することになるため、管理・処分が大変になります。
改正後:侵害額請求
贈与と遺贈があるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担するため、第三者Aに対して500万円、兄に対して500万円の支払いをそれぞれ求めることができます。
第三者Aも兄も私にお金を支払えば不動産を手放す必要はありません。不動産の共有関係が発生しないので、権利関係が明確になります。
遺留分侵害額の請求方法
遺留分の権利がある相続人は、贈与または遺贈を受けた人に対して、遺留分を侵害されたので、その侵害額に相当するお金を支払うよう請求することができます。
請求するときは、後日の証明のために相手方に対して配達証明付き内容証明郵便で行うと安心です。
意思表示をしないまま一定の時間が過ぎると、権利がなくなってしまうので注意しましょう。
遺留分侵害額請求権の時効は、次のいずれか早い方です。
- 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
当事者で話し合いがつかない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を申立てることができます。
なお、調停の申立てだけでは、相手方に対する意思表示になりませんので、注意が必要です。
相続人以外の者の貢献を考慮する特別寄与料の創設

従前の民法では、亡くなった方の子どもの配偶者(長男の妻など)が献身的な介護や亡くなった方の事業拡大に貢献していたとしても、相続人ではないとの理由により遺言書がない限り遺産の分配を受けることができませんでした。
このような不公平を解消して相続人以外の親族の貢献に報いるため、今回の改正法において、相続人以外の親族が、亡くなった方に対して生前に無償で介護等を行い、これにより亡くなった方の財産の維持・増加に特別に寄与したといえる場合には、介護等を行った親族は相続人に対して寄与度に応じた金銭の支払いを求めることができるとの制度が新設されました。
この寄与度に応じた金銭を特別寄与料といいます。
特別寄与料については、「法改正に対応 寄与分と特別寄与料について」もあわせてご覧ください。
特別寄与料が認められる条件
特別寄与料を請求できるのは、次の条件を満たした場合です。
- 亡くなった方の、相続人ではない親族
親族は、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族をいいます。
ご本人のいとこの子どもが5親等の血族、配偶者の甥姪が3親等の姻族ですので、親族の範囲は結構広いです。
その中で、相続人ではない人が対象です。相続放棄をした、相続人の欠格事由に該当する、廃除によって相続権を失った人は対象外です。 - 無償で、療養看護や家業の手伝いなどをした
療養看護などの対価をもらっていた場合は、特別寄与料を別途求めることはできません。亡くなった方がお礼や報酬としてお金などを渡す契約をしていたり、遺言を残していた場合も「無償」とは言えなくなります。なお、従来からある相続人が対象の「寄与分」制度では、亡くなった方に対して生前お金の援助をしていた場合も「寄与分」となりますが、「特別寄与料」制度では、除外されます。そのため、亡くなった方の介護費としてお金を払っていただけでは、「特別寄与料」は請求できません。
- 亡くなった方の財産の維持・増加に特別に寄与
療養看護などの行為によって、亡くなった方の財産が減らずに済んだ、債務が増えなかった、財産が増えた、債務が減った、ということが必要です。そして、「特別に寄与」というのは、「一定の財産をあげないと不公平だし、亡くなった方もあげたいと思うだろう」という程度の貢献を意味するとされています。
一方、従来からある相続人が対象の「寄与分」制度での「特別の寄与」は、亡くなった方との関係上通常期待される程度を超える高度な貢献が求められます。
手続きの流れと期限
特別寄与料の請求は遺産分割手続とは別に行われます。
特別寄与料の請求にあたっては、相続人との協議によって決定することもできますが、協議が調わない場合や協議をすることができない場合には、家庭裁判所に対して「特別の寄与に関する処分調停」を申立てることができます。
注意すべき点として、特別寄与料には請求の期間が定められています。
具体的には、請求者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月又は相続開始から1年のいずれか短い期間内しか請求できません。
特別寄与料の請求を検討している場合には、できるだけ早めに準備をすることが大切です。
夫婦間の不動産贈与における持戻し免除の意思表示の推定規定の創設

遺産分割においてよく問題になるテーマとして特別受益があります。
特別受益とは、亡くなった方から生前に結婚や生活などのために贈与を受けていたり、遺言により贈与を受けたという場合における、贈与された財産のことをいいます。
特別受益は、遺産の前倒しとみることができるため、贈与を受けた財産に相当する分を遺産にプラスして、贈与を受けた相続人の相続分から減らす調整が行われます。
これを、特別受益の持戻しといいます。
一方、亡くなった方が、「持戻し免除の意思表示」をしたときは、遺産分割時にその贈与・遺贈を特別受益として扱わずに計算することができます。
夫婦間の自宅の贈与について特別受益として持戻しがされる(=自宅の贈与分を取り分から差し引かれる)と、残された配偶者の取り分が減ってしまい、亡くなった方が残される配偶者の将来の生活のために自宅を贈与する行為が無意味となってしまう問題がありました。
そこで、改正法は、20年以上の結婚期間がある夫婦の間で自宅の生前贈与や遺言による贈与がされた場合には、遺産分割において特別受益の持戻しをする必要がないこととなりました。
今回の改正によって、残された配偶者の生活の安定がより一層図られたといえます。
特別受益について詳しくは、「特別受益って何?仕組みや計算方法について」をご覧ください。
持戻し免除の意思表示の推定規定が適用される条件
- 婚姻期間が20年以上の夫婦
居住用不動産の贈与または遺贈時に婚姻期間が20年以上であることが必要です。例えば、婚姻10年目で贈与があって、婚姻25年で亡くなった場合、適用されません。
また、「婚姻期間」は、法律婚のみで、事実婚は含まれません。 - 居住用不動産の贈与または遺贈
この制度の目的は、配偶者の老後の生活保障なので、対象となる不動産は居住用のみです。投資用不動産、事業用不動産(店舗)や別荘などは対象外です。自宅兼店舗のような不動産の場合は、その不動産の構造や形態によって個々に判断されます。
- 亡くなった方が「持戻し免除」と異なる意思表示をしていない
この制度は、あくまでも「推定」なので、亡くなった方が「持戻し免除」と異なる意思表示をしている場合は、適用されません。
例えば、遺言書に「妻への居住用不動産の贈与は、遺産分割において持戻して計算すること」という一文があった場合は、「持戻し免除」と異なる意思表示をしていることになります。
亡くなった方による「持戻し免除を認めない」という意思表示は、口に出したり文書に書いてあるなど明示的なものだけでなく、「黙示の意思表示」も含みます。
持戻し免除がある場合とない場合の比較
夫は婚姻22年目に妻に自宅の土地と建物(時価3000万円)を贈与
遺産は預金3000万円
- この制度の適用あり(=持戻し免除の意思表示の推定)
遺産:預金3000万円
妻:3000万円×1/2=1500万円
子:3000万円×1/2×1/2=750万円妻の取得分:預金1500万円+自宅3000万円
子の取得分:各預金750万円 - この制度の適用なし(=持戻し免除と異なる意思表示あり)
遺産:自宅3000万円+預金3000万円=6000万円
妻:6000万円×1/2-3000万円(自宅)=0円
子:6000万円×1/2×1/2=1500万円妻の取得分:預金0円+自宅3000万円
子の取得分:各預金1500万円
まとめ
これで、今回の相続法改正についての解説は終わりました。全部で4回に分けて解説することが必要になるほど、多くの規定が新設されたり変更されたりしました。
特に残された配偶者の方は、配偶者居住権など新しい権利が創設されていますので、大きな変化があったといえます。
今回の改正は社会情勢に法律を合わせるために行われた改正ですので、その内容を知っておくことはみなさんにとってとても大事になります。
ご自身が亡くなったときに備えてこれから遺言書を作成なさりたい方や、今後のご家族の相続について不安や疑問をお持ちの方はもちろんのこと、すでに遺言書を作成している方にも、今回の法改正は関係してきます。
相続に関してご不安がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。