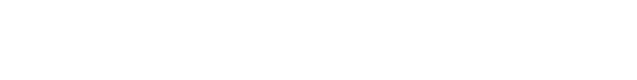相続・遺言コラム
約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第1回)~改正の背景について~
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士
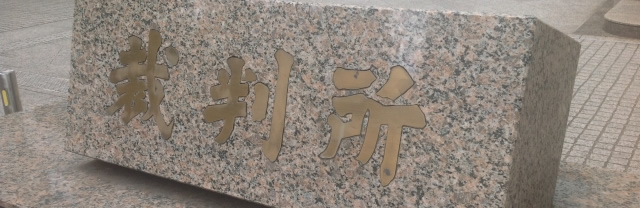
相続法とは、誰が相続人となるか、遺産がどのように受け継がれるか等の相続に関するルールを定める民法上の規定をいいます。今般、相続に関する規定が大幅に改正され2018年7月13日に改正法が公布されました。今回の法改正は、1980年の大幅な改正から約40年ぶりとなる大きな改正です。
改正法は原則として2019年7月1日に施行されています。ただし、自筆証書遺言の方式を緩和する規定は2019年1月13日に他の改正より先行して施行され、配偶者居住権に関する規定は2020年4月1日に施行されました。最後に、「自筆証書遺言の法務局保管に関する法律」という新しい法律が2020年7月10日に施行され、これで、相続に関する新しいルールがすべて出揃いました。
改正によって変更又は創設された事項は以下のとおりです。
- 自筆証書遺言制度に関する見直し
- 配偶者居住権の創設
- 相続人以外の者の貢献を考慮する特別寄与料の創設
- 夫婦間の不動産贈与における持戻し免除の意思表示の推定規定の創設
- 遺留分制度に関する見直し
- 遺産分割制度に関する見直し
- 相続の効力等に関する見直し
この改正事項について解説していきます。
第1回目の今回は、相続法が改正された背景について説明をします。
第2回目は、自筆証書遺言制度と配偶者居住権制度について
第3回目は、遺産分割制度、相続の効力等について
第4回目は、遺留分制度、特別寄与料、持戻し免除の意思表示の推定規定についてです。
法改正の背景
これまでも相続法の細かな改正は行われてきましたが、大幅な改正は約40年ぶりです。
40年の間に社会は大きく変わり、また、法律の規定を補足する裁判所の判断も多く出されました。
今回の改正は、そのような社会経済情勢の変化等に対応するために行われたものであり、大きく分けて、少子高齢化から配偶者保護の高まり、家族の在り方の多様化等への対応、実質的公平の確保に対する高まり、裁判所の判断の明文化やルールの明確化、という4つの柱があります。1つずつその内容をみてみましょう。
少子高齢化から配偶者保護の高まり

「人生100年時代」といった言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。さすがにまだ平均寿命は100歳に到達していませんが、厚生労働省が公表したデータによると、2019年の平均寿命は、男性が81.41歳、女性が87.45歳です。40年前の1980年の平均寿命は、男性が71.73歳、女性が76.89歳でしたので、40年間で男女とも10歳も平均寿命が延びています。
平均寿命が延びているということは、一方配偶者が亡くなったときに、残された配偶者が高齢であるということです。
高齢になると、生活環境の変化が心身に大きな影響を与えることが多く、できるだけ生活環境をそのままにすることが生存配偶者のためになります。また、その後の人生がまだまだ続くことが考えられますので、生存配偶者のその後の生活を保護する必要があります。
これに対し、生存配偶者と同じく相続人である子どもは、両親の一方が亡くなったときにはすでに経済的に独立しており、遺産を必要とする経済状況ではないことが多くなります。
また、少子化によって子どもの人数が減っていますので、相続によって取得する財産の割合は相対的に増えていることになります。
そのため、生存配偶者と子どもとを比べたとき、保護の必要性は生存配偶者の方が相対的に高まります。
このようなことから、改正法では、残された配偶者の生活を保護することを目指した規定が設けられました。
具体的には、配偶者居住権という新しい権利の創設や、長期間婚姻している夫婦間で行われた居住用不動産の贈与の優遇などです。これらについては、次回以降のコラムや「配偶者居住権とは?利用した方が良い場合・良くない場合」で解説しています。
家族の在り方の多様化等への対応

これまでは法律婚が一般的でしたが、現在は、婚姻届けを提出していないけれども夫婦同然の生活をしている事実婚の人や、同性のパートナーとともに生きている人など、家族の在り方は多様化しています。
そのため、法律婚を前提にした相続法の規定では、不平等や不公平が生じてしまう場合があります。
とはいえ、様々な家族の在り方すべてに対応した法律の規定を作ることは困難です。
このようなときに活躍するのが遺言です。
遺言を作ることによって、遺言者の意思で法律の規定を修正して財産を分けることができます。
遺言には、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
特別方式の遺言は、死期が迫っているときや遭難したとき等の特殊な状況にあるときの遺言なので、事前に準備することはできません。
事前に準備することができる遺言は普通方式の遺言になり、それには、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言の種類についてはコラム「遺言書を書くメリットと種類」ですでに解説していますので、そちらをご覧ください。
普通方式の遺言のうち、もっとも手軽で費用をかけずに作成できるのが自筆証書遺言です。
ただ、これまでの自筆証書遺言は利用しづらい面があり、また、せっかく作成しても誰にも見つけてもらえず最終的にはその遺言に従って財産を分けることができないこともありました。
そのため、今回の改正では、この自筆証書遺言をもっと活用できるように規定が改正されたり新しい法律が作られたりしました。
具体的な内容は次回以降に解説をしますが、自筆証書遺言の作成方法が緩和されて作成がしやすくなり、遺言書保管法という新しい法律が制定されて自筆証書遺言を法務局が保管してくれたりするようになりました。
実質的公平の確保に対する高まり

相続人は複数いることが多いです。そのため、法律には相続人間の公平を保とうとする規定があります。
例えば、相続人である子どもが複数いたときに、そのうちの1人のみが、両親の営んでいる事業を自分の仕事の合間を縫って助けてあげてその事業の拡大に貢献した場合や、両親の介護を行っていた場合に、その点を考慮せずにすべての相続人を平等に扱ってしまうと、実質的には不公平になってしまいます。
そのため、亡くなった人の財産の維持・増加を助けた相続人は、遺産に対して「寄与分」という一定範囲の権利が認められています。これによって、財産の維持・増加を助けていない相続人との公平を図っています。
しかし、あくまでもそこでは相続人の間での公平しか考えられていません。
例えば、夫の妻は夫の両親の相続人ではありませんので、いくら事業の手助けや介護を行って財産の維持・増加を助けたとしても、遺産分割の場面では何も考慮されません。これでは実質的に不公平になってしまいます。
このようなことから、今回の改正によって、相続人以外の親族との実質的公平を図ることを目指した規定が設けられました。
具体的には、相続人ではない親族が財産の維持・増加を助けたと認められる場合に、その親族が相続人に対してお金を請求する権利を認める特別の寄与の制度が新しく設けられました。この点については、「法改正に対応 寄与分と特別寄与料について」ですでに解説をしていますので、そちらをご覧ください。
また、相続人間の公平を図るための手続きをより簡易にすることを目指した規定も設けられました。
裁判所の判断の明文化やルールの明確化
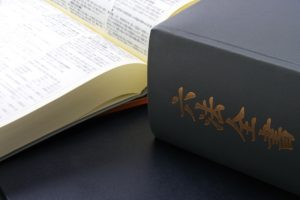
相続法は、日本国憲法の制定に伴って1947(昭和22)年に家督相続制度の廃止など全面的な改正がされましたが、時間的な余裕がなかったため、憲法の規定に反している規定は削除されたものの、憲法の規定に反していない規定はひとまずそのままにされました。
そのため、相続法は将来改正する必要があるとの決議がなされていました。しかし、その後も全面的な見直しがされなかったので、裁判所の判断によって多くのルールが補足されてきました。
今回の改正で、これまでに出された裁判所の判断が法律の規定として明文化されました。
例えば、遺留分について、相続人が複数いる場合の割合についての規定がなく、判例によって法定相続分の規定が準用されてきましたが、改正によってそのように明文化されました。
逆に、裁判所の判断を修正する規定も設けられました。
例えば、裁判所は、遺言によって法律で定められた割合を超える相続分を指定された相続人は、そのことを相続人以外の人に対抗要件がなくても主張できると判断していましたが、新しい規定は、法律で定められた割合を超える分については、相続人以外の人に権利を主張するためには対抗要件がなければならないとしました。
これ以外にも、遺言をその内容通りに実現させる人を遺言執行者といいますが、その遺言執行者の権限に不明確な点があったため、これが明確化されたりしました。
まとめ
以上のように、今回行われた法改正は、新しい権利が創設されたり新しいルールが付け加わったり、とても大きな改正です。相続はみなさんにとってとても身近な事柄ですので、新しいルールについてわからないことがあれば、遠慮なく弁護士にご相談ください。