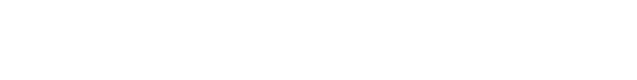相続・遺言コラム
新制度!遺言書保管所に遺言書を預ける~預けた後に遺言者ができること~
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士
はじめに

2020年7月10日から、国の機関である法務局の遺言書保管所に自筆証書遺言を預ける新制度が始まりました。
制度のメリットや、遺言書保管所に遺言書を預ける手続きについては、当事務所のコラム「新制度!遺言書保管所に遺言書を預ける~保管手続について~」で解説しましたので、ご覧ください。
遺言書を遺言書保管所に預けた後に、「遺言書の内容を忘れてしまった。もう一度確認したい。」と思うことや、「引っ越したので住所が変わった。」という場合や、「やっぱり手元で遺言書を保管したい。」と思うこともあると思います。
今回のコラムでは、遺言書を預けた後に遺言者ができる手続きを解説します。
今回解説するのは、遺言者本人と、遺言者の法定代理人(親権者や成年後見人等)が行うことができる手続きです。相続人等は、できる手続きや手続きの時期、請求書の形式などが異なりますので、注意してください。
まずは、遺言書を預けた後にできる手続きを一覧表で確認します。必要書類等はそれぞれの手続きで異なっていますが、手続きの大きな流れは同じです。流れを確認した後で、各手続きの内容について解説します。
遺言書を預けた後にできる手続き
遺言者が遺言書を預けた後にできる手続きは、
①預けた遺言書を閲覧する手続き
②住所や名字などが変わったときの変更手続き
③遺言書保管所での保管をやめる撤回手続き
の3つです。
それぞれ比較すると以下のようになります。
| 閲覧手続き | 住所などの変更手続き | 保管の申請の 撤回手続き |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 遺言書の 原本の閲覧 |
スキャンした遺言書をモニターで閲覧 | ||||
| 手続きできる人 | 遺言者本人のみ | 遺言者本人 | 遺言者の法定代理人(親権者や成年後見人など) | 遺言者本人のみ | |
| 手続き場所 | 遺言書原本が保管されている遺言書保管所 | 全国の遺言書保管所 | 全国の遺言書保管所 (郵送でも可) |
遺言書原本が保管されている遺言書保管所 | |
| 必要書類と 持ち物 |
①請求書 ②本人確認証 ③手数料(収入印紙) |
①届出書 ②変更が生じた事項がわかる書類(住民票の写し等) ③本人確認証 |
①届出書 ②変更が生じた事項がわかる書類(住民票の写し等) ③請求者の本人確認証 ④法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本や登記事項証明書等) |
①撤回書 ②本人確認証 |
|
| 予約の有無 | 要予約(氏名などの変更手続きを郵送でする場合は不要) | ||||
| 費用 | 1回につき 1700円 |
1回につき 1400円 |
不要 | ||
大きなポイント3つ
それぞれの手続きの細かい点は後で解説しますが、大きなポイントは3つです。
まず、住所や名字などの変更手続きは、単なる事実の変更で、変更の有無は住民票の写しなどで確認できます。そのため、遺言者だけでなく遺言者の法定代理人なども手続きできますし、郵送でも行うことができます。
それ以外の手続きは、遺言者が遺言書保管所に行って直接行わなければいけません。
次に、遺言書の原本が必要になる手続きは、原本を保管している遺言書保管所でなければできません。原本の閲覧と、撤回の手続きです。それ以外の手続きは、全国どこの遺言書保管所でもできます。
最後に、費用がかかるのは閲覧手続きのみです。それ以外の手続きには費用はかかりません。
手続きの流れ
すべての手続きは遺言書の保管手続きと同じ流れですし、注意点も異なりません。念のため、確認します。
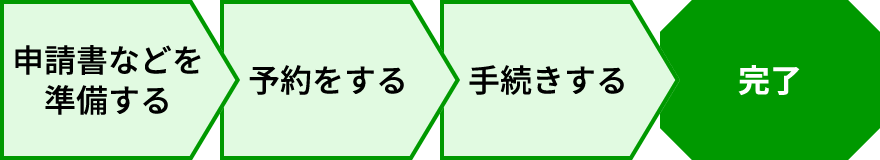
1.申請書などを準備する
手続書類は、遺言書保管所の窓口でも法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html)でも入手できます。それぞれの申請書などのURLは以下の通りです。
・遺言書の閲覧の請求書
(https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321934.pdf)
・住所などの変更届出書
(https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321936.pdf)
・遺言書の保管の申請の撤回書
(https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321935.pdf)
申請書はA4普通紙に片面で印刷します。機械で読み取りますので、印刷のときに拡大・縮小などをしてはいけません。また、印刷した申請書や窓口で入手した申請書をコピーして使うとズレが生じてしまって機械で読み取れなくなるかもしれませんので、避けた方がいいでしょう。
申請書に記入するときの主な注意事項は次のとおりです。
・チェック欄は明瞭に記載する
・2桁の数字は頭に0を付けない
・左詰めで記入する
そのほかのそれぞれの記載例や注意事項のURLは以下の通りです。確認したうえで、申請書を作成しましょう。
・遺言書の閲覧の請求書
(https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/02_kisairei.pdf)
・住所などの変更届
(https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/04_kisairei.pdf)
・遺言書の保管の申請の撤回書
(https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/03_kisairei.pdf)
2.予約をする
住所などの変更手続きは郵送でも行えますが、それ以外は遺言書保管所で手続きをしなければいけないので、手続きをする遺言書保管所に必ず予約をしなければいけません。
予約は、
①専用ホームページ(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action)(24時間365日)、
②電話(平日8:30~17:15)、
③窓口(平日8:30~17:15)
でそれぞれ予約できます。
予約は、本人の名前でします。ご夫婦やご友人などと一緒に手続きをしたくても、1人ずつ予約をしなければいけません。
3.手続きする
持ち物を持って、予約した日時に遺言書保管所に行きます。予約時間を過ぎてしまうとキャンセル扱いされてしまうかもしれませんので、時間に間に合うように余裕をもって行きましょう。
持ち物は手続きごとに少し異なりますが、2点ほど共通しています。
1つは、申請書類です。機械で読み取りますので、汚れないようにして持って行きましょう。
もう1つは、本人確認書類です。なりすましを防ぐため、必ず写真付きでなければいけません。
各手続きの内容と注意点
では、どのような場合にどの手続きを利用すればいいのか、注意点も含めて各手続きを解説していきます。
閲覧手続き
遺言書保管所には遺言書そのもの(原本)を預けてしまいます。
そのため、手元控えを持っていないと、「遺言書の内容を忘れてしまった。もう一度確認したい。」と思うことがあると思います。
そのようなときには、「閲覧手続き」を利用します。
閲覧手続きには、2種類あります。
預けた遺言書そのもの(原本)を閲覧する方法と、スキャナーで読み込んだ遺言書の画像をモニターで閲覧する方法です。
比較すると以下のようになります。
| 原本の閲覧手続き | モニターでの閲覧手続き | |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 遺言者本人のみ | |
| 請求場所 | 遺言書原本が保管されている遺言書保管所 | 全国の遺言書保管所 |
| 必要書類と持ち物 |
①請求書
②本人確認証 ③手数料(収入印紙) |
|
| 予約の有無 | 要予約 | |
| 手続費用 | 1回につき1700円 | 1回につき1400円 |
原本閲覧とモニター閲覧の違いは2つ
1つは、閲覧できる場所です。
原本の閲覧は預けた遺言書そのものの確認ですので、実際に預けた遺言書保管所に閲覧請求をしなければいけません。預けた遺言書保管所は、保管証に記載されています。
もう1つは、手続き費用です。
原本の閲覧の方がモニターでの閲覧よりも費用が高くなっています。
それ以外は、両手続きとも共通しています。
注意点:遺言者以外と一緒に閲覧できない
どちらの手続きも、遺言書保管官など職員の面前で遺言書原本あるいはモニターを閲覧しなければいけません。
これは、遺言者以外が確認しないようにするためです。付き添った家族や友人なども閲覧することはできません。
住所などの変更手続き
遺言書を預けた後に、「引っ越したので住所が変わった。」という場合や、「結婚(離婚)して名字が変わった。」という場合があると思います。
遺言者本人だけでなく、受遺者や遺言執行者がいる場合にその人たちにも同じような状況の変化があると思います。
また、「死亡時通知対象者を変更したい。」という場合もあると思います。
そのような場合には、住所などの「変更手続き」をしなければいけません。
死亡時通知対象者については、「新制度!遺言書保管所に遺言書を預ける~保管手続について~」でご確認ください。
変更手続きは、他の手続きと同じように予約を取って遺言書保管所に行って手続きをすることもできますが、郵送で行うこともできます。また、遺言者本人だけでなく、遺言者の法定代理人が行うこともできます。
注意点:内容の変更はできない

注意すべきことは、変更手続きは「遺言書の内容を変更したい。」というときに利用する手続きではないということです。
遺言書保管所に保管できる遺言書の通数に制限はありませんが、遺言書の内容を変更したい場合には、後述する「保管の申請の撤回手続き」をとったうえで、新たに民法の規定に従った遺言書を作成しなおすのが良いでしょう。
遺言書は何度でも、一部または全部を書き直すことができますが、複数の遺言書があった場合、新しい遺言書に書かれている内容が効力を持ちます。
自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、遺言書保管所に保管してあるかは関係ありません。一部だけを変更すると、どの部分が変更されて効力を持つのかわかりにくく、ややこしいので、全部を書き直した方が良いです。
変更できる事項
変更手続きで変更ができる事項は、次のとおりです。
【遺言者について】
・氏名
・出生年月日
・住所
・本籍
・筆頭者の氏名
・国籍
・電話番号
【受遺者等・遺言執行者等について】
・氏名
・住所
・出生年月日
・会社法人等番号
【死亡時通知対象者について】
・指定した死亡時通知対象者の氏名
・指定した死亡時通知対象者の住所
・指定した死亡時通知対象者を別の人に変更
保管の申請の撤回手続き
「遺言書を遺言書保管所ではなく貸金庫で保管したい。」という場合や、「遺言書を作り直したいので保管してある遺言書を一旦手元に戻したい。」という場合には、保管の申請の撤回手続きをします。
撤回手続きは、遺言書の原本を返還してもらいます。
そのため、遺言書原本を保管している遺言書保管所でしか手続きできません。
また、遺言者の住所や名字などが変わったのに変更手続きをしていなかった場合には、申請時の住所等から現在の住所等に変更になったことを証明する書類を添付しなければいけません。
注意点:保管の申請の撤回は遺言書の効力と無関係
注意が必要なのは、保管の申請の撤回手続きは遺言書の効力とは無関係ということです。
撤回手続きをしても遺言書の効力は無くなりません。
撤回手続きは、あくまでも遺言書保管所での保管をやめるという手続きにすぎません。
撤回手続きをして手元に戻ってきた遺言書をそのまま自宅などで保管すれば、新たに遺言書を作らない限り遺言書の効力は保たれます。
おわりに
遺言書保管所に預けた後も、遺言者の状況の変化に応じた様々な手続きが用意されています。手続きの選択や方法がわからない場合は、遺言書保管所にお問い合わせください。
また、遺言書保管所では遺言書の内容について相談できませんので、遺言書の内容に関しては弁護士にご相談ください。